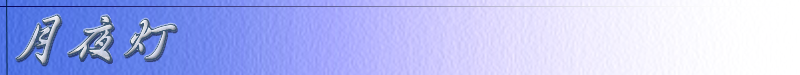
閑話 朔の日、神殿での一幕
エルを信仰する民にとって、月の満ち欠けと言うものは大きな意味を持つ。守護神エルは光と水の神であったと言う伝承を元に、一月のうち最も光の無い時間帯、つまり月のない新月の夜を忌む風習があるからだ。神の御力が届かない朔の夜は魔の闊歩する時、魅入られたくなくば外に出るな……と言うのはどこの神殿でも語られる教えの一つで、デュランベールの民ならば誰もが知る常識の一つだった。
国王陛下のお膝元と言う立地もあり、神殿の影響力が地方よりも弱い王都であっても、朔の日が特別な日であることに変わりはない。夜間に外出する者のため、王都の中央神殿で魔を退けるための儀式を行われるのだ。その措置に至るまでにかつて神殿と軍、商人達まで交えて散々裏で利益の擦り合わせがあったそうだが、そのような裏事情は今を生きる者たちには然程関係の無い話である。
その日、朔の日の長い礼拝を終えたシーギスは、些か疲れた顔で神殿内の自室へと戻っていた。そのような大きな儀式を取り仕切るのも、神殿の最高責任者である彼の職務の一つだ。家を継いでから何度となくこなしてきたとは言え、数時間にわたり人前で話し続けるその仕事を、シーギスはあまり得意としてはいない。
書類が並べられた机の前に腰を下ろし、ぼんやりと宙を見上げる。礼拝は苦手だが、かと言って書類仕事が得意かと言うと首を傾げざるを得ないのが辛いところだ。薬を煎じたり病人の治療にあたったり、信仰と関係の無い雑務であれば喜んで参加するのだけれど、当主になってしまった今それも難しいのが現状だった。
「失礼します、神官長様。あの、裏口からお客様が……応接間にお通ししています」
「ああ……解った。すぐ向かう」
ノックの音とともにおずおずと声をかけてきたのは、最近神官見習いになったばかりの少年だ。彼のように、神殿で育てられた孤児が神官として働くことは珍しくない。貴族を訪ねてくるような客人の相手を任せるには不安だが、元より神殿にシーギス個人を訪ねてくるのはマナー違反だ。然程気にする必要もない。
一枚も進んでいない書類を一瞥すると、シーギスは神官服の上にマントを羽織り部屋を出た。約束もなく裏口から来る相手など限られているが、念のため貴族としての様相は整えておく必要がある。いつ何が起こるか解らないのが、貴族社会と言うものなのだ。
ほどなくして到着した応接間で待っていたのは、見慣れた装いをしたシルヴェストルの当主だった。概ね予想が当たったことに、シーギスは僅かに肩の力を抜く。ここに訪ねてくる人間は幼馴染である彼とカーラが殆どで、多くの場合は火急の面倒事を持ってやってくるのだけれど、それでも見ず知らずの相手よりは年上の幼馴染達の訪れのほうが気楽なことに変わりはない。
「礼拝明けか? 忙しいとこ悪いな」
「いや……大丈夫だ。今日はどうした?」
「大口顧客への納品に不備があったら信用問題だからな。たまには視察しておかないと」
悪びれもなく建前を言葉にするエセルに、シーギスは溜息をつく。彼の言葉に嘘はない。薔薇加工品を大規模に扱う彼の家から、神殿で使用する聖水の材料を一括で購入しているのは、紛れも無い事実だからだ。とは言え、わざわざそれだけの為に訪ねて来るほど彼が暇ではないことは、シーギスとて良く知っている。
「人払いはしてある。早く本題に入れ」
「言うようになったな、お前も。まぁ話が早くて助かるよ」
くすりと微笑むと、エセルは懐から小さなカードを取り出してテーブルの上にそっと置いた。見慣れぬ柔らかな筆跡で細かく文字が綴られたそれに、送り主が解るような情報は何も書かれていない。
「カーラが動いた。今夜、スヴェンと聖地で密会する予定らしい。……俺が人を置いてるのは掴んでるだろうに、真っ向から仕掛けてきた意図は読めないけどな」
「聖地……今夜は新月だし、目当てはエルか」
「俺らを釣るのが目的でなきゃそうだろうな。そっちに関してはお前の領分だ、俺は多くは口出ししないけど……スヴェンの奴がバシュラールに取り込まれるのは避けたい」
新月のエルは危険だと言うのは、彼の守護神のしでかした事を知る者たちの間での共通認識だ。人によっては王城の敷地内に居るだけで気分が悪くなるほどで、朔の夜は聖地から人払いをするのが通例となっている。
あいつは過激派だから、と肩を竦めたエセルは、エルの件、ひいてはスヴェンの件においても完全に保守的な立場を貫いている。何をしでかすか解らないイレギュラーを刺激したくないと言うのが本音のようで、その一点においては概ねシーギスとも利害は一致していた。なるほどだからここに話を持ってきたのか、と行きついた結論に内心頷いていれば、コツコツと机をノックする音で目の前の男に注意を引き戻される。
「お前さ、一応他所の家の当主が交渉事に来てるんだから、そうあからさまにぼうっとするなよ」
「……すまない」
「そうやってすぐ謝るところも良くない。お前のほうが立場は上なんだから、相手につけ入る隙を与えるな」
言い聞かせるように話す内容こそ厳しいが、苦笑混じりのその声音は気軽なものだ。成人して年齢の差は気にならなくなり、身長に至ってはとうに追い越したが、十五で家を継いだエセルと大災害後になし崩しで当主になったシーギスとの間には、埋めがたい経験の差が横たわっている。家の格にこそ差があれど、代替わり後の慣れない業務に翻弄される中で何だかんだと世話を焼いてくれた相手に、未だに頭が上がらない部分も多い。
「まぁ、天下のヴェルデ家を嵌めようなんて輩はそう居ないだろうからいいけどね……それで、今夜の件。どうする気だ?」
「そうだな……相手があのカーラだ、穏便に阻止できるとは思えない。聖地近辺での揉め事は避けたいし、今夜は見逃すしかないだろう。……後手に回ることになるが、スヴェンは後から説得する。明け方に聖地に向かえば間に合うだろう」
「了解。今回は全面的に協力するよ。丸め込みは俺のほうが得意だしね」
そう緑の目を細めると、エセルは出された茶に手をつけることもなく席を立つ。来るのは突然だが、余り長居をしていかないのも旧友たちに共通する特徴だった。そうやって都合よく友と仕事相手の顔を使い分ける彼らに苦言を呈したところで、口の回らないシーギスに勝ち目は無いに等しいのだけれど。
それぞれの思惑が絡み始める中、新月の夜は更けて行く。