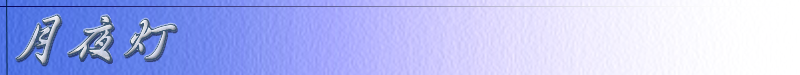
閑話 ある夏の夜の一幕
デュランベールの王都デュラン、その最も高き場所。聖地と呼ばれるその土地には、限られた者以外足を踏み入れることはない。静かに閉ざされたその場所で、国王であるオルランドは暮らしていた。
それは暗く静かな夜のこと。夜半にふと目を覚ましたオルランドは、何かに誘われるように窓辺へと向かった。分厚い布を手繰り外を除けば、宵闇色の空一面に深紅の花弁が舞っている。現においてはオルランドの目にしか映らぬその光景は、幻想的で美しくはあれど、哀しい。
この大地を覆わんばかりに降り続けるそれは、はらはらと零されるエルの涙だ。心を持たぬ神であるエルの抱えた淀みが、こうして夜毎に降り積もる。触れればまるで融けるように消える赤は、この地を覆う雪より余程儚く、脆い。
「……陛下。あまり夜風に当たられては御身体に障ります」
ふわりと、肩にガウンが掛けられる。窓辺に居たのはさほど長い時間では無かったはずなのに、気付けば指先は氷のように冷え切っていた。それを悟られぬよう、オルランドは気遣わしげにこちらを見下ろすラディスに向き直る。
「すまないね、起こしてしまったかな」
「陛下の御前で近衛が寝る訳には参りません」
何度となく交わしたやり取りに、思わず苦笑が零れる。この生真面目で忠実な臣下は、思えば幼い頃からそうだったように思う。王位を継ぐだなんて考えたことも無かった、遠い昔から。
「……この国は、救われるんだろうか」
未だ花弁の舞う空へと視線を戻し、オルランドは呟いた。
「エルの力がもたらした奇跡は、何度となくこの国を救ってきた。それは、今のエルの依代である僕が、きっと一番知っている」
だからきっと、今この時にも意味があるはずだ。オルランドは、そう何度となく嘯いてきた。その言葉を信じる者が居らずとも、それが王の使命で、エルの三百年分の記憶を知り得る数少ない人間としての義務だった。
けれど彼は、エルが悪魔でないのと同様に、全能の神でないことも知っている。
「僕がオルランドである前に国王でいなければならないように、エルにも成すべきことがある。エルの意志がどうあれ、エルの力はこの国のために働くようにできているんだ。……だとすると、スヴェンは何のために喚ばれたんだろう。……この国で、この海の底で、これからいったい何を成すんだろう」
ぽつりぽつりと、独白のように言葉を零す。オルランドの目から見てスヴェンは異質ではあったけれど、特別な才があるようには思えなかった。貴族の在り方とは違うものの民としては然程変わった所もなく、英雄になり得る器かというと首を傾げざるを得ない。それでも彼は確かに、エルの祝福を受けた存在だった。ならばきっと、彼は何かを成し得るのだろう。
「戻れるのかな。昔のような、光ある日々に」
「……無くしたものは、戻りません。死んだ人間が生き返ることもない」
「そうだね。兄様も、父上も、もう帰ってはこない。それはエルの力を以てしても不可能なことだ。……だけど、僕はまだ生きている。まだ、賭けられるものがある。新たな時代の礎になることだって……」
「オルランド」
咎めるような低い声に、曖昧な笑みを向ける。忠臣であると同時に友でもある彼は、表情こそ乏しいものの情が薄い訳ではない。王としてではないただのオルランドのことを最も案じているのは、彼だと言える程度には。
「……僕はみんなみたいに優秀じゃない。僕の価値なんて、この身に流れる創国王の血だけだ。だからエルが……この国が、デュランの末裔たる僕を必要としなくなったなら、その時は……きっと、王として一つの時代の幕引きを求められるんだろう」
「貴方は貴方だ。国のために殉ずる必要はない」
「同じ言葉を返すよ、ラディス。……友として、その言葉だけは有難く受け取っておくけれど……でも、それは王にしかできない務めだからね。他のことのように、みんなに甘える訳にはいかないんだ」
軍にはカーラとラディスが、内政にはフランとエセルが、そして神殿にはシーギスが居る。優秀な彼らに任せてさえ居れば、オルランドが何もせずとも、何も出来なくとも問題なく国は回っていた。お飾りの愚君だと陰口をたたかれるのも仕方がないと思えるくらいに、オルランドは無力だ。
本音を言えば、玉座になどつきたくはなかった。王の子として生まれはしたものの、父と兄を支え、彼らの影となり生きる道もあるはずだった。それが変わってしまったのは偶然か、それとも必然なのか。
「つい弱音を吐いてしまったね……例え何かが起こるとしても、それは今日や明日の話ではないよ。そんなに心配しなくても大丈夫。……まだ、僕にもエルの加護はあるようだから」
窓から僅かに身を乗り出して、空を舞う赤にそっと手を伸ばす。指先が触れれば花弁は消え去り、代わりとばかりに温い風が優しく頬を撫でていった。両の眼には映らずとも確かに感じるエルの気配に、オルランドは僅かに頬を緩める。エルがオルランドの中に流れる血を欲している限り、彼がこの深い海の底で独りになることは無い。
「……どうかこの国に、全ての民に、エルの祝福が与えられますように」
謳うように紡いだ哀れな王の言葉が、静かな闇へと融けていく。