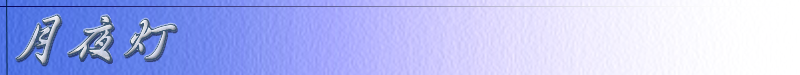
そこは、只々静かな所だった。
薄暗くて物寂しいその空間に、幼子が一人横たわっている。漆黒の髪と白磁の肌、そして鮮血を思わせる瞳を持った、どこか人形めいた印象の少女。十にも満たない年頃のその娘は、冷たい石の床に倒れ伏したまま、指先一つとして動かすことはない。一枚の絵画のような、完成された光景。
その傍ら、ほんの数歩の距離に男は居た。ここがどこなのか、彼女は誰なのか。それどころか、自分が何故ここに居るのかさえ男は知らない。そんなものは知らずとも構わないし、知る方法もないと言う事だけは、何故か理解していた。
『…………』
男の目線の先で、少女の薄紅色の唇が微かに震える。彼女が零したのは微かな吐息一つ。けれど、男にはそれで十分だった。呼ばれているのだ。『姫』が、自分の助けを必要としている。
赤い瞳に吸い込まれるように、男は歩みだす。応えなければならなかった。彼女の言葉は絶対で、逆らうことは許されないのだから。
一歩、二歩。足を踏み出すごとに、身体は重くなっていく。視界は歪み、酷く喉が渇いていた。けれど、あと少し。彼女の元に辿りつけさえすれば、すぐに、楽になる。
「これ以上はダメだよ」
不意に、男の歩みが止められる。何が起きたのか、知覚するより先に男の身体は地面に沈んだ。ざらざらとした床の感触と腕を捻りあげられる痛みが、心地よい気だるさを払って行く。
「王国に仇なす存在は、排除しなくてはならないね」
見知らぬ、けれどどこか懐かしい顔をした青年が、僅かに震える少女に向かってそっと手を伸ばした。それを合図に、柔らかな光が辺りを包み込む。彼の髪と同じ木漏れ日の色に照らされ、薄暗い、少女のための世界がゆっくりと融けて行く。
『いや……たすけて、おにいさま……』
「……これは全て悪い夢。目が覚めたらきっと、全て忘れてベッドの上だよ。さぁ、目を閉じて……ゆっくり、呼吸をして」
少女のか細い声を遮るように、青年はくるりと男に向き直る。彼の言葉に呼応するように、頭の芯がじんわりと痺れていく。薄れていく意識の中で、もう一度少女を見遣る。もう彼女に、あの異常なまでの魅力は感じられない。ただの幼子が一人、そこに横たわっているだけだ。
「そんな顔、しないで」
青年の冷たい指先が男の頬をそっと撫でる。果たして自分はどんな顔をしているのか、問うてみたくはあったが言葉は紡げそうになかった。ゆっくりと重たくなっていく瞼の裏で、赤と金と黒とがぐるぐると踊る。
「おやすみなさい。もう、ここへは来ないでね」
勝手なことばかり言う男だ。心の中で呟いた言葉が、伝わったのか否か。
沈みきった意識の底。何もない静寂の中、誰かが笑ったような気がした。