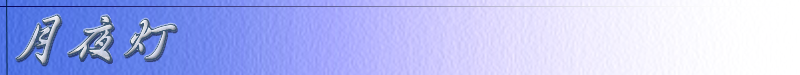
目の前の『敵』の身体が傾ぎ、倒れる。一瞬後、大きな水音が辺りに響き渡った。
「勝者! 『海上の覇者』、スヴェン!」
間髪入れず響いた声に被せるように、空を割るような歓声が上がる。会場中が彼の、どこの馬の骨とも知れぬ平民の勝利に沸いていた。観客から目を背けるように水面を見遣れば、今まさに水から引き上げられたばかりの対戦相手と視線がかち合う。よく沈みそうな豪勢な鎧を纏った男は、こちらを射殺さんばかりに睨みつけていた。
沢山の歓喜と僅かな憎悪に熱狂するこの場の中心に立っていながら、スヴェンの心は誰よりも冷めきっていた。こんな八百長まがいの勝利になんて、何の意味も見い出せはしない。貴賓席で満足げに微笑む連中のことを思えば、今すぐここから逃げ去ってやりたいくらいだった。
けれどそれが叶うはずもなく。彼はただ、これ以上なく不名誉な『名誉』に苦い表情を浮かべることしかできないでいた。
その夜、デュランベール王都の貴族街において、大規模な晩餐会が開かれた。晩餐会など、つい先日まで貴族社会などに縁もゆかりもなかったスヴェンには全く馴染みのないものである。豪勢な食事に気分が高揚したのも束の間、見ず知らずの貴族達に囲まれて延々と下らない会話を聞かされるだけの時間に、楽しめる要素など欠片もありはしなかった。
「……しかし、今回は久々とは思えぬ大盛況でしたな。流石はシルヴェストル卿、そのような隠し玉を用意して居られるとは人が悪い」
「陛下が即位なされてから初めての闘技会ですからね。主催という栄誉を授かった以上、全力を尽くさねばなりませんから……」
さてこの話はいったい何度目だったろうか。心の中で指折り数えながら、スヴェンは欠伸を噛み殺すことに尽力していた。何があろうと絶対に口を開くな、豚が鳴いてるとでも思って頭だけ下げておけ……と、きつく言い含められていたからだ。
失礼極まりない指示の出所は、先ほどからシルヴェストル卿などと言う大層な名で呼ばれ続けている目の前の男である。金細工のような長髪にエメラルドの瞳、如何にも貴族ですと言わんばかりの豪華かつ高価そうな装いは、その年若さも相まって貴族だらけのこの空間の中でも一際目を引いていた。だがそれを指摘したところで、主催なんだから当然だろ、と呆れ顔で応えるだろうことは想像に難くない。ここ一月で少なからず彼の人となりを知っているスヴェンとしては、建前だらけのこの晩餐会には薄ら寒い思いしか抱けなかった。
「……シルヴェストル卿。少し構わないだろうか」
それからしばらくの後。歓談の空気を裂くように、冷やかでよく通る声が広間に響いた。カツカツと踵を鳴らして近づいてきたのは、闇を切り取ったような漆黒の長髪に、こちらも宝玉のような紫の瞳を持つ青年だ。服装は派手さこそないが最礼装と言われる類のもので、気味が悪いくらいに整った顔立ちも相まって会場の視線を一身に集めていた。茶番の終わりを察し内心で安堵したスヴェンを目で制し、シルヴェストルの名を持つ男は優美な仕草で礼をする。
「これはこれは、バシュラール卿。わざわざこのようなところにまでいらっしゃるとは、何か火急の用事でしょうか?」
しんと静まり返った会場中が、固唾を呑んで二人のやり取りを見守っていた。バシュラールとシルヴェストルはどちらも国王陛下の『お気に入り』だが、派閥や思想、家の格の差もあり不仲で有名である。公の場で揉め事を起こすほどどちらも愚かではなかろうが、よもや巻き込まれはしなかろうかと戦々恐々としているのだ。
「宴も闌のところすまないが、陛下が此度の件で話を、と仰って居られる。……そこの男も含めて、だ」
「陛下が、でございますか……有難き幸せにございます。では、急ぎ準備を致しましょう」
「ああ。馬車は此方で用意してある。余り陛下をお待たせするな」
言い捨てるようにして踵を返すバシュラール。それを見送り、よく通る声で閉宴を告げるシルヴェストル。そして、その短い会話の間ただの一度も目を合わせなかった二人に、少しずつざわつき始める会場。三者三様のその様子を余所に、誰からも注目されていないスヴェンは抑え損ねた大きな欠伸を零した。
「……お前さぁ、いくらなんでもアレは感じ悪くないか?」
「煩いな。お前の腰が低すぎるだけじゃないの? いくら新参だからって、媚び売りは程々にしてもらわないとみっともないくて見てられない」
「はいはい。流石、大貴族のバシュラール様が言うことは一味違うな」
ところ変わって馬車の中。見物客の視線から開放された『不仲』の二人は、すぐ隣に座るスヴェンのことなど蚊帳の外ににして喧々轟々とやり合っている。
「そもそもこういう計画にした時点で、私が泥被るのは見えてたと思うけど? 中立派が相当そっちに流れるよ。家格はともかく、エセル個人のことは気に入ってる奴も多いから」
「でも長期的に見れば痛み分けだろ。全くの余所者に対して王のお側に侍る権利を与えるんだ、保守派の連中に散々言われるのは目に見えてる。元々あいつらは俺のこと嫌ってるし、嬉々として叩いてくるだろうさ。勿論、カーラを旗頭にして」
「勘弁してよ……何かある度神輿にされるのは懲り懲り。上手いこと往なしといて」
ぼんやりと窓の外を見つめながら、スヴェンは二人の会話を聞き流す。今の二人の様子をあの場にいた貴族連中に教えてやったら、一体どんな顔をするのだろう。国随一の『不仲』の二人がまさか愛称で呼び合うほどの仲だなんて、話したところで本気にはしないだろうが。
種を明かせば簡単な話だ。家柄の違い、思想の違いから彼らの意見が対立しがちなのは事実だが、彼らはそもそも『不仲』と言うほど嫌いあってなどない。それどころか、同じ王に仕える者としてかつては友として過ごしたこともあると言う。それが、解りやすい対立構造があった方が便利だからと言う身も蓋もない理由で、人前では立場を偽っているのだ。
「……怖えな、貴族ってのは」
ため息とともに零した言葉に、一方は苦笑し、もう一方は怪訝そうに顔を歪める。言うなれば、この国の有力者たちはすっかり騙されてしまっているのだ。それも、まだ精々成人して数年というこの年若い者たちの手によって。それを恐ろしいと言わずしてどうしろと言うのだろうか。
「ま、腹芸の一つや二つできなきゃ生きてけないのは確かだからな。特に、今回みたいに無理を通す場合は」
そう笑って見せたのは、シルヴェストル家当主であるエセルバート・シルヴェストル。王を含め極近しい間柄でのみエセルと呼ばれるその男は、旧友と話すような気軽さでスヴェンの肩を叩いた。本人いわく三世代ほど前に貴族になったばかりだと言う彼は、このデュランベール王国においてスヴェンの後見人と言う扱いになっている。身体一つでこの国に来たスヴェンにとっては恩人であると同時に、諸悪の根源とも言える存在だ。
スヴェンを闘技会で優勝させ、その功績を理由に王の傍に侍る資格、すなわち貴族に準ずる権利を与える。
そんな荒唐無稽な計画が成功してしまったのは、このエセルの人脈と財力によるところが大きかった。闘技会を開催すること、そして船乗りであったスヴェンのために水上競技を新設すること。その他にも、王国軍から素行が悪く実力がない部隊を選んで闘技会に出場させ、確実にスヴェンが勝てるような環境を整えること。それらの権謀は、ほとんどが彼の発案によるものだった。
「だから怖えっつってんだろ。こんな嘘つきばっかりで大丈夫なのかよ、この国」
「本音と建前を使い分ける頭がないなら黙ってなよ。この国に、愚かな連中に気を遣ってやる余裕はない」
吐き捨てるように言葉を返したのは、バシュラール家当主代理で国王の名代も務めるカラヴィアン・バシュラール。同じく愛称をカーラと言う黒髪の彼とは数度顔を合した程度の仲だが、それでも十分に解る程度には気難しい気質の男だった。
発案がエセルならば、それを実現可能にしたのは彼である。軍の総帥にして王の血族、そして王国随一の大貴族であるカーラの発言力は、庶民のスヴェンの想像を遥かに超えていた。発言がいちいち辛辣なのもそう言った立場が影響しているのだろうと、スヴェンは半ば無理矢理自身を納得させている。無論気分は良くないが、貴族相手にそれを言いだしても仕方がないことくらい、流石の彼も承知していた。
デュランベールにおいて、身分と言うものが占める要素は絶対と言っていいほど大きい。それはスヴェンが生まれ育った、名も知らぬ港町であっても変わりはなかった。名ばかりの法こそあるものの、領主である貴族はまるで虫を潰すかのように平民の命を奪うし、平民はそれに逆らう術を持たない。だからこそスヴェンは貴族が嫌いで、逃げるように海に出たのだ。それが何の因果か、貴族に散々世話になった挙句、自らもその身分を与えられようとしている。
人生、何があるか解らない。そんな言葉を胸に深く深くため息をつく元平民を乗せ、馬車はゆっくりと王城へと進んでいった。