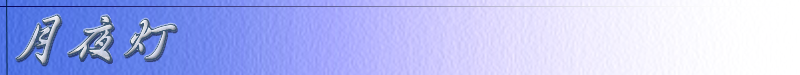
「シルヴェストル卿よりご紹介賜りましたナターシャと申します。よろしくお願いいたしますね、スヴェン様」
そう優雅に礼をした女は、釣り目がちの気の強そうな顔立ちをした美女だった。艷のある赤毛は高い位置で纏められ、大胆に顕にされた細い腕や首を強調している。大きく切れ込みの入ったドレスの胸元にさり気なく目をやれば、大きく張りのある二つの果実が僅かに覗く。悔しいが、エセルの言った通り文句のつけようがない『お目付け役』だった。
外見の素晴らしさもさることながら、それを差し引いても彼女との時間は中々に充実したものとなった。彼女の少し低めでしっとりとした声が耳に心地良いのは勿論だが、賢く博識、かつ少しばかり下世話な会話にも成通した彼女は、離宮で退屈を持て余していたスヴェンにとってはありがたい話相手となっている。惜しむらくはその肢体に触れようとするとさらりと躱されてしまうところだが、その躱し方もまた絶妙だった。
端的に言えば、元より頭脳労働には向いていない質であるスヴェンは、小難しい考え事などすっかり忘れて美女との逢瀬にハマってしまっている、と言った具合であった。
「お邪魔するわね、スヴェン。昨晩は良く眠れたかしら?」
「おう。独り寝じゃなけりゃもっとよく寝れたかも知れねぇけどな」
「あらあら……そんな事仰って、メイドの娘に手を付けたりなさったらダメよ? ここに働きに来ている子たちは預かりものですもの」
スヴェンにそう微笑みかける彼女は、毎日シルヴェストル家の家臣に連れて来られ、日が沈む前に迎えと共に帰っていく。話題はその時々で様々だが、最近は貴族達の噂話などが主だろうか。身分は高くないが貴族社会には成通しているという彼女の持つ情報は、真偽はともかく幅広い。
「昨日は……そう、確か先代のレスタンクール卿のお話だったかしら」
「あー、とんでもない絶倫だったって話だったっけか。王家のご令嬢から敵国の姫さんまで選り取りみどりとは羨ましい話だよな」
「ふふ、でも庶子も含めれば両手両足でも足りない数の御子がいらっしゃったから大変だったって噂よ。当代様にはお目にかかったことがないから、詳しいことは存じ上げないのだけれど……血を分けた兄弟が敵になることなんてどこにでもある話だもの」
ほっそりとした指で小さくも豪奢なティーカップをつまみ上げると、ナターシャは優雅な仕草で口を潤す。彼女の連れの下女が入れたこの紅茶は、どこか気取った味がする気がして少しばかり苦手だった。どうせなら酒の一杯でも、と誘ったことはあるが、そちらもやんわりと断られてそのままだ。
「子供なんぞははどうでもいいが、ハーレムってのは男なら誰しも一度は憧れるもんだろ?」
「あら……あなたも今は貴族なのでしょう? 手の届かないお話ではないわ。年嵩の貴族の方々はほとんど側室をお持ちでいらっしゃるもの」
「そうは言ってもなぁ……じゃあアンタに求婚したら受けてくれんのかよ?」
「ふふ、こんな年増を煽ててどうするの。貴族のご令嬢の適齢期より倍も上なのよ? もっとお若い方をお選びなさいな」
「アンタの半分じゃ完全にガキじゃねぇかよ……」
そう苦い顔をするスヴェンの頭にふと思い浮かんだのは、この数日すっかり忘れていた夢の中の少女の姿だった。思い返して見れば確かに将来に期待できそうな容姿をしていたが、彼女は精々スヴェンの3分の1程度の歳月しか生きていないだろう。
「若い娘は対象外かしら? 黒髪赤目の美少女を探しているっておっしゃっていたから、てっきりそちらも大丈夫なものだと思っていたのだけれど」
「流石にねーわ……つーかその話アンタにしたっけか」
「いいえ。でもシルヴェストル卿から少し、ね。でも残念ながら私の調べられる範囲では条件に合致する娘は居なかったわ。髪の色も目の色も稀少だもの。特に漆黒の髪なんて、王家に連なる方意外では殆ど見かけないんじゃないかしら」
デュランベールは幾つかの人種が混ざり合い暮らす土地ではあるが、大多数を占める民族の髪色は暗い灰色か茶色だ。スヴェンのような金髪を始めとした鮮やかな色味の髪の毛は東方や南方の血を継ぐ者に多いらしく、街ではよく見かけるが貴族には多くない。そんなことをつらつらと話しながら、ナターシャは肩にかかる後れ毛に指を絡ませる。
「そんなに珍しいもんか? 俺が前に居た街じゃ黒い髪もそれなりに見かけたもんだが」
「そうね……この国は余所者に厳しいから。それに、創国の英雄で最初の国王となったデュラン様が黒髪黒目だったから、少し特別視されているのもあるわ。昔は黒髪や黒目の子が産まれたらデュラン様の欠片を持つ子供としてエル様に捧げていた、なんて噂話もあるくらい。そうして淘汰されたから黒髪の子は居ないんだ……なんて、ね」
「またとんでもない噂だな……この国の宗教屋もそんなエゲツないことしてんのかよ」
「まさか、流石に眉唾物よ。信憑性があるお話だったらこんな所で口にはしないわ。神殿で孤児の引き取りはしているけれど、下手な所に奉公に出されるより余程恵まれた環境だそうよ。それに……」
口元に手をあて品よく笑うナターシャの言葉を、コツコツと言う几帳面そうなノックの音が遮った。姿を見せたのは、スヴェンは名も教えてもらっていないナターシャの下女だ。その手には、小さな白い封筒が握られている。
「失礼いたします、ナターシャお姉様、スヴェン様。お手紙を預かって参りました。きちんとした身なりの方でしたが言伝はなく、差出人の名も記載されておりません」
「あ? なんだそりゃ、うっかりしてんな……まぁ中見てから考えるか」
「……流石にこの場所にそんな不届き者はいないでしょうけど、贈りものにはお気をつけになったほうがよろしくてよ。少し失礼するわね」
手紙に手を伸ばしたスヴェンを制し、ナターシャが封筒を手に取った。彼女の細い指が、閉じ目に押された赤い封蝋を指し示す。よく見ると、一角獣と三本の剣が刻み込まれている。
「貴族や商人の方からのお手紙だと、だいたいこうして印が押されて居るの。知らない印のお手紙は疑ってかかったほうがいいわ。……これはバシュラール家の紋章ね。略印だから私用だと思うけれど、親しい方でもいらっしゃるの?」
「あー…………全然親しくはねぇが、知らん仲でもないな。紋章とやらのことは知ったこっちゃねぇけどよ。アンタは知ってるか? あの妙にお綺麗で神経質そうな顔した黒髪の……ってあいつも黒髪だな」
「ええ……軍部の総司令官様ね、存じ上げているわ。確か、バシュラール家に降嫁された王女殿下の二人目の御子息だったはずよ……あまりお気の長い方ではないそうだから、早く確認したほうが良いんじゃないかしら」
ナターシャに促されるまま封を開ければ、几帳面に整った文字で『今夜聖地で』とだけ綴られたメモが姿を見せる。中を覗こうと逆さにしようと、それ以外には何もかも入ってはいない。勿論署名も、宛名さえも無しだ。
「こんだけかよ……それなら適当にそこらの連中捕まえて伝言すりゃいいだけじゃねぇか」
溜息とともに、スヴェンはメモを放り投げた。ひらひらと舞った小さな紙片が、ソファーの上にゆるりと着地する。
「ふふ、大貴族様ですもの、仕方ないのよ。それにしても……月のない夜の呼び出しだなんて、少し怖いわね。闇は人を狂わせるものだから」
「はぁ……アンタまでオカルト話かよ」
「残念ながら、これもただの噂話のようなものね。でも夜の街では有名よ、実際に満月の夜よりも新月の夜のほうが恐ろしい事件は多いってお話もあるし、余程のことがなければ女は出歩かないわ。……遠くに行くのでないなら心配はいらないでしょうけれど、貴方もよくお気をつけて」
常になく真面目そうな表情でそう告げるナターシャに、スヴェンは頷くしかできなかった。
そしてその日の深夜。渋々聖地に向かったスヴェンを出迎えたのは、予想通り黒髪の美丈夫だった。随分待たされたのだろう、至極不機嫌そうな表情を浮かべては居たが、スヴェンの知った話ではない。今夜、という雑な指定しか寄越さなかったのは相手の方だ。
「よう。美形が凄むと迫力やべぇな」
「はぁ?」
射殺しそうな視線を向けてくるカーラに、スヴェンは肩を竦めて見せた。お忍びなのだろうか、前回会ったときとは打って変わって、カーラの服装は一般兵と同じものだ。髪も邪魔にならないようにまとめ、眼鏡までかけて徹底的に印象を変えている。しかし、さほど物覚えの良くないスヴェンにさえ一目で見つけられているようでは、その効果は薄いとしか言えない。
「……まぁいいよ。今夜はこれからエルのところに向かう。シーギスや神官連中は今夜は居ないはずだけど、邪魔が入らないうちにさっさと始めるよ」
「おいおい……俺はあんなトンデモ経験もうごめんだぜ。それにエルならこないだ会ったばっかじゃねぇか、そんなしょっちゅう奇跡なんぞを起こさせていいのかよ」
「お前が見たのはエルの表の顔だけだよ。他の連中もそれぞれ勝手に動いているようだし……折角だから、娼婦にうつつを抜かして飼い慣らされたアホに、奴の本性を見せてやろうかと思ってね」
整った面に嗜虐的な笑みを浮かべ、カーラは早足で中庭へと向かう。星明かり一つなく、虫の声一つ聞こえない静かな夜。前回以上に不気味な闇の中、スヴェンは再びエルの元を目指すこととなった。