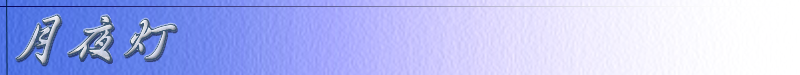
「十歳未満の少女、ですか」
「おう。お前なら知ってるかもってシーギスの野郎が言ってたぜ」
翌日。スヴェンは塔の少女の正体を求め、フランの元を訪れていた。この国の文官を統べる立場にある彼は、王宮内の事象に限れば誰よりも詳しいはずの立場である。その分仕事も多いはずだが、生来の優秀さ故か然程忙しそうにする様子もなく、突然の来客を追い返そうとする素振りは無かった。
「確かに他の方々よりも僕のほうが可能性は高いですが……その前に一つ確認させてください。貴方は、夢の中の話を事実だと受け止めているんですか? この国は海の底に沈んでいると言う……」
「それに関しちゃ、別に信じるも信じないもねーだろ。どっちにしたって部外者の俺には関係ねぇよ」
軽く肩をすくめると、スヴェンは近くの棚に無造作に寄り掛る。デュランベールと言う国に愛着の無い彼にとって、この国が雲の上にあろうと海の底に在ろうと然程変わりはない。元の土地に帰れないのは少しばかり残念だが、こうして貴族連中に取り込まれている時点で、地続きであろうとなかろうと解放は絶望的なのだ。それならば、考えるだけ時間の無駄だと言うものだろう。
「それともなんだよ、俺が信じない方があんたらにとって都合良かったか?」
「いえ……ただの事実確認です。深い意味はありません。……本題に入りましょうか。始めに言っておきますが、その少女が実在するとしても、見つけるのは困難だと思われます。まず書面上では調べる手立てがありませんから」
ゆるりと立ち上がると、フランは壁際に置かれたポットを傾けた。小柄な彼の手には幾分大きなそれから、琥珀色の液体が注がれていく。
「貴方の嫌いな貴族の慣習に基づくことですが……ある程度の年齢になるまで、子供の存在は秘匿されるのが一般的だからです。男児であれば公に何らかの役割を担う時、女児ならば婚約が決まる時に、初めてその家の一員として認められ名を与えられます。婚姻の話が出るのは早くても十歳ですから、その少女がどこかの貴族の娘として登録されている可能性は低いでしょう。……ああ、別にこの話は忘れても構いませんよ。貴方にはおそらく不要な情報です」
「へいへい、ご親切にどーも」
肩を竦めるスヴェンに、小ぶりなカップが手渡される。使いこまれた風情のあるそれは、特段客用というわけではないのだろう。書類と本とに埋もれた小さな部屋は事実上のフランの執務室で、端から客を迎えるようには作られていないらしかった。椅子だって机と揃いの一脚しかなく、それも大柄なスヴェンが座れるようなものではない。それでも応接室などという肩の凝る場所に通されるよりはよほどマシな心地だった。
「ではまず、貴方の見たものの分析から始めましょうか。まず塔の名やエルの言葉から判断して、『星』が少女を暗示している、とするのが素直な解釈かと思います。ここまではよろしいですか?」
「あー……いいんじゃねぇかな」
いいも悪いも解かんねぇけど、と言葉を繋げると、フランは呆れたように軽く首を振った。緩やかにうねる茶髪がふわふわと揺れる。他の貴族たちに比べれば長くはないその髪は、それでも肩ほどまでの長さがあり、彼の幼い容姿を少女めいた印象に飾っている。
「興味は無いようですが、一応説明しておきますね。宗教的に星は未来や真実、希望の象徴として扱われることが多いです。手が届かないものと言った意味もありますが……貴方の星、という表現をされたそうなので除外して良いかと思います。そう言ったものが落ちていく、と言うのは凶兆と捉えられるでしょう。黒い髪と赤い目と言うのも少し気にはなりますし……」
一度言葉を区切ると、フランは僅かに目を伏せ茶を啜る。それに釣られるようにカップに口をつけると、ふわりと甘い香りが口内に広がった。きっとこれも目玉が飛び出るほど高いんだろうなぁ、と気を散らしていると、カップの中身と似た色の瞳にじとりと睨まれる。
「……星見の塔は建国以前、神殿とともに聖地にあった塔の名です。創国王デュランとともにこの地の平定に尽力したとされる聖女エステルがその命を終えた塔として、エステルの塔の異名で一般には知られています。残念ながらとっくの昔に風化して、今は祭壇が残るのみですが」
「はぁ……急にどうした?」
「聖女の最期は、塔からの投身自殺だったそうです。この国のために血肉を捧げたと、美談として扱われています」
ことりとカップが机に置かれる音が、やけに大きく響いた。ぼんやりと傍らに置かれた本を見つめながら、フランは感情の乗らない声で言葉を続ける。
「貴方が見たのは三百年前の亡霊かもしれませんね」
「……マジで言ってんのかそれ」
「さあ。僕は可能性の話をしているまでです。あまり嗅ぎ回ることはお勧めしませんが」
一目で作り笑顔だと解る笑顔を浮かべ、フランはそう話題を終えた。
「……で、フランのところで油売ってて俺との約束忘れたって訳か」
与えられた部屋に戻ったスヴェンを出迎えたのは、待ち構えていたエセルの呆れ顔だった。必要なものを仕立てたから昼に持っていくと言伝てられてはいたのだが、使者の長ったらしい挨拶とともにすっかり聞き流してしまっていた。待ちぼうけを喰らわされた形になるエセルだが、その表情に怒りの色はない。
「まぁ良いけどな、急ぎの用があった訳じゃないし……それにしても、聖地に行ってたって言うのに随分元気だな。もう少し消耗してるかと思った」
「は? 一晩寝なかったくらいでどうにかなるほどヤワじゃねーよ」
「そう言う話じゃなくて……エルの『奇跡』は、合わない奴が受けると調子崩しやすいんだよ。偶に大丈夫な奴も居るけどな」
軽く肩を竦め、エセルは持参した荷物を広げ始めた。普段着から礼服までの洋服一揃えに装飾品、挙句は武器や防具の類。それら全てに着用できる場所や場面の制限があるそうだが、彼の話ではそれは別段覚えておく必要はないということだった。下働きのものに言えば着付けてくれるから、などとあっさりと言う辺り、多少気安い印象はあってもやはり貴族と言うことか。
「……これ後で金払えとか言わねぇよな?」
「言われても無理だろ。今回は必要経費ってことにしといてやるよ。うちの商品だからそこまで損が大きい訳でもないし」
エセルを当主とするシルヴェストル家は、貴族でありながら商人のような仕事も多く受け持っている。服や布の類に限らず王国の物流は全て彼の掌の上、などと言う噂もあり、それなりに顔は利くから欲しいものが在るなら調達してくるよ、などと言っていたのも記憶に新しい。
「……なぁ、アンタ人探しは得意か?」
「モノによる。フランが匙投げたようなものだと難しいかもしれないな」
「子供だ。十歳……いや、七、八歳くらいの娘で、黒い髪に赤い目。ガキらしくもない、真っ黒の高そうなドレスを着てた。見た場所はあの聖地だから、おそらくこの辺りのガキなんじゃねーかって思ってるんだが……」
「聖地の話か……少しばかり難しいな。聞いただろうけど、そもそも王宮に女子供は殆ど居ないから」
何の話だ、とスヴェンが首を傾げると、エセルは意外そうに翡翠色の目を瞬かせた。フランかシーギスが教えたかと思ってたけど、と言う前置きに首を横に振ると、彼は僅かに声を落とし話し始める。
「大災害のことは聖地で聞いたんだろ? その時に第22代目の国王陛下が亡くなって、今の国王陛下が即位なさったんだけど……あの方は元々王位を継ぐつもりではなかったから、それなりに問題は起きたんだよ。そのうちの一つに、後宮への放火事件ってのがあってさ」
言葉を紡ぎながら、懐から取り出したメモに『D330年10月 大災害とそれに伴う騒乱発生』と流れるような字で書き記す。DXX年、と言うのはこの王国で一般的に使われている暦の表記方法だそうだ。尤も、公式文書に触れる立ち場で限り然程馴染みがある訳ではないという注釈がつくが。
「細かい情報は公開さなかったけど、先王の側室や妾、女官や宦官の連中もみんなその時に命を落としてる。シーギスの見立てによると、災害時と同じくエルの干渉があったんじゃないかって話だ。……それ以来、念のため女子供は王宮に入らないよう取り計らってる」
エセルはさらさらと要点を書き留めると、半分に折り畳んだ紙片をスヴェンの胸ポケットに捩じ込んだ。指先で軽くペンを玩びながら、流石にこれで忘れないだろ?と彼は笑う。
「……じゃあ今はその後宮とやらは無人ってことかよ。全員死んじまったのか?」
「一応、生き残りはゼロ、って報告はされてる。今の陛下は未婚だし、無人なのは間違いないと思うけど」
「なんか引っかかる言い方だな……なんか知ってんなら勿体ぶらず教えろよ。減るもんじゃねぇんだから」
「さて、どうだろう。これ以上はタダじゃ話せないな」
恨めしげなスヴェンの視線に完璧な笑顔を返し、エセルはソファーから立ち上がった。軽く伸びをし黄金色の髪をばさりと払うと、思い出したようにスヴェンに向き直る。
「ああ、そう言えば、近いうちにお前にお目付け役をつけることになった。いつまでも俺らがつきっきりって訳にもいかないしな。聖地でのことは話すなよ? 王国内でも陛下と俺達しか知らない国家機密扱いだ。漏らしたら処刑されかねない」
「いや、ついでで言うようなことじゃねーだろそれ。最初に言えよ……まぁ、んなことわざわざ言われなくても、そんなトンデモ話誰にも言いやしねぇけど」
「でもお前は、そのトンデモ話を疑わずに信じたんだろ? 流石エルの見込んだ英雄様ってところか。……お目付け役については楽しみにしてろよ。お前好みの相手を見繕ってやるから」
そう言い置くと、エセルはひらひらと手を振りながら部屋を後にした。急に静かになった部屋に残されたのは、彼に届けられた大量の荷物とポケットの中のメモ用紙のみだ。謎の少女についての情報は、収穫なしと言っても過言ではない。
たかが夢だと割り切って忘れてしまえばいいのだろうが、スヴェンはエルに『星』と称された少女が不思議と気になっていた。彼女を見たとき、あの鮮血色の瞳と目があった時の既視感が、何故か頭から離れないのだ。ぼんやりと思いを巡らせていると、不意にフランの言葉を思い出す。
「『三百年前の亡霊』……か。冗談じゃねーよ」
ぽつりと呟いた声は予想より掠れ、誰も居ない部屋に寂しく響くのみだった。