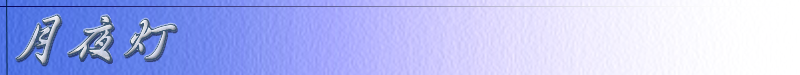
デュランベールの短い夏が終わり、王都に吹く風に僅かばかりの肌寒さを感じ始めた頃。貴族街の片隅に構えたスヴェンの屋敷に、一通の手紙が届いた。両翼を広げた不死鳥の紋が描かれたその書面は、国王から下された収穫祭への参加命令であった。
「収穫祭は年に一度、秋に行われる祭典です。春蒔きの麦や芋類の収穫、また家畜を潰し冬越しのための保存食とする時期に合わせ、神殿が主導して各街単位で開催されています」
それから数日の後。スヴェン邸の食堂に乱雑にと並べられた古びた椅子に腰掛け、ラシュレイ家当主ことフランデリク・ラシュレイは相変わらずの平坦な声音でそう説明を続けた。
「王宮で開催される収穫祭は民間のものとは趣が異なり儀式的な意味合いが強く、貴族として登録された全ての家の参列を必要とします。半分は領地を持つ者達から効率的に税を徴収するための建前ですね。貴方は領地も資産も収入もないので納税の必要はありませんが、貴族身分である以上は儀式への参加義務は発生します」
「はぁ……とりあえず書かれた日時に王宮行けばいいのかよ?」
「その辺りの段取りについては僕の担当外なので、そのうち誰かが説明に来るかと」
スヴェンの質問をさらりと受け流すと、フランは饗された焼き菓子を摘み口へと運ぶ。彼から屋敷とともに預かった料理人の作った菓子は中々の美味で、それを目当てにか彼は時折この屋敷を訪れていた。出不精のフランにしては珍しいことだが、それだけその料理人の腕が良いということなのだろう。材料費さえちゃんと渡せば三食美味い飯を食わせてもらえるのだから、スヴェンとしても否やはない。
「……ああ、そう言えば応接室も本で埋まっていましたっけ。何とかなりそうですか?」
「おう、片付いてるぜ。お前が寄越した執事が一から十までいちいち細かく掃除の計画立ててくれやがったからな」
スヴェンが視線を向けると、扉脇に控えた土気色の顔をした男が緩慢に頭を下げた。彼もまたこの屋敷のオマケでついてきた使用人で、陰気極まりない顔と性格さえ除けば有能な執事であった。彼の差配がなければ、スヴェンは今頃まだ厩で寝起きする羽目になっていた事だろう。
「お役に立っているなら何よりです。念のため、部屋を確認させていただいても?」
「へいへい、ご案内すりゃいいんだろ、ったく。てめぇの屋敷なんだから好きにしろっての」
すっかり空になった皿とカップを残し、フランとスヴェンは殺風景な廊下を抜けて応接間へと向かう。フランから鍵を受け取った時点で、本が散らばっていないのは水回りだけ、埃と蜘蛛の巣に至っては見当たらない場所が無い程の有様だった割には、随分と見られるようになったものだとスヴェンは胸を張った。本を捨てるなと厳重に言いつけられている以上、その分奥の部屋に物が増えただけだと言うことは考えないことにしている。
大きなソファーとローテーブルだけが置かれた応接間を覗けば、日当たりの良い窓際には小さな人影があった。先日エステルと言う名を与えられたばかりのその少女は、数冊の本を足元に積み、一人静かに読書に勤しんでいるようだ。部屋に入ってきた男たちに気付いてない訳ではないだろうが、その視線は本に留め置かれたまま動かない。
「少し見ない間に随分と自発行動が増えましたね」
「まぁな、飯も自分で食うようになったし、最近じゃ勝手にそこらの本を持ち出してきて読んでるぜ。まだ喋ったりはしねぇけどな」
「おや、その本は貴方が与えたわけでは無いんですね……『魔術体系総論』ですか。子供の好むような本だとは思えませんが」
開かれたページを一瞥し、フランが首を傾げる。つられるように手元を覗き込むが、細かな文字がびっしりと記載されたそれは見るからに難解そうで、子供でなくとも好んで読む者は少ないように思えた。少なくともスヴェンならば、給金に上乗せがあっても読みたくはない代物だ。
「……つーか、この家そんな本まであるのかよ」
「ええ、殆どが禁書扱いで世間に出回ってはいませんが……その本はクラーヴ・アージェントという魔法学者の著作ですね。信仰と魔術の関係性を体系立てて考察した、魔法という題材を扱う中では比較的信憑性のある学術書だと言われていたそうです。彼の著作は聖女エステルの持ち込んだ多数の書物の中にいくつか含まれていたそうで、歴史的資料の一つとしてラシュレイ家の管理下に残されています」
「あーそうかよ……魔法なんてもんにガクジュツだのシンピョウセイだの言われてもなぁ」
「現代の常識ではそう考える人が大多数でしょうね。記載内容だけ見れば矛盾は無く、旧時代の迷信だと断ずるには根拠が足りないのが困ったところでもあるのですが。……繰り返しになりますが、これは禁書です。屋敷を任せた以上貴方や彼女が読む分には構いませんが、他人には見せないようにしてくださいね。内容がどうあれ、所持自体が違法とされるものですから」
そう釘を刺すと、フランは目線を合わせるようにエステルの隣に膝をつく。お世辞にも子供の相手に向く性格ではないように見えるが、案外彼らの波長はあっているようだった。スヴェンからしてみれば、何を考えてるかわからない子供が二人、と言った印象だけれど。
「エステル。その本が気に入ったのであれば、同じ作者の書いた生物学の本も中々に興味深いですよ。『魔獣はなぜ滅びたのか』などはちょうど今読んでいる内容とも密接に繋がる内容ですし、竜や一角獣など有名な伝承生物の生態にも触れられています。一巻は客間の右奥三列目の山にあるはずですので、良ければどうぞ」
「……よく覚えてんな、そんなことまで。そういう与太話が好きだったなんて意外だぜ。アンタは地に足ついてるほうかと思ってた」
「好き嫌いに関係なく、蔵書は内容から置き場所まで全て把握していますよ。それがラシュレイの仕事でもありますし、幸い記憶力には自信がありますから。……何でしたら、お好きな本を言って頂ければこの場で諳んじることもできますが」
「それは流石にきめぇよ」
そうでしょうねと淡々と相槌を打つと、長いローブの裾を揺らしてフランは立ち上がる。その表情は常の通り、あまり楽しげとは言い難い作り笑顔だ。
「ともかく、大人しく本を読んでいられるようなら彼女の件については安心です。今後客人が増えるかとは思いますが、くれぐれも他の者達に気取られないようにしてくださいね」
「へいへい。ったく、一度聞きゃ解るっての」
「そうですか。では本題に戻りますが応接間と廊下については大いに改善の余地があります。寝室の隣にある倉庫の奥に絵画が数点置いてあるはずですから、適宜合うものを飾ってください。布類の掛け替えも必要かと思いますので、そちらはラシュレイの名で発注して頂ければ大丈夫です。それから……ちゃんと聞いてますか?」
「あー……俺が聞いてなくても、有能な執事様が聞いてるから大丈夫だろ。そんないっぺんに言われて覚えられるかよ」
扉の影で気配なく立つ執事が、水を向けられぺこりと頭を下げた。僅かばかり呆れの色を滲ませるフランの背を軽く叩き、スヴェンはふらりと部屋を出る。屋敷を任されたとは言え所詮は雇われの身。言われるがまま掃除と子守に追われる日々を送っている彼に、貴族の自覚など芽生えているわけもない。
―――収穫祭まで、あと一月余り。単調で平穏な日々は、一歩ずつ終わりへと近付いてゆく。