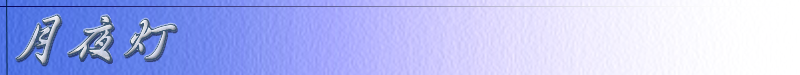
重い沈黙に支配された部屋に執事が入ってきたのは、それから短くはない時間が経った後だった。フランとスヴェンとを見比べ逡巡する彼を軽く手を振って追いやり、ふかふかと柔らかな背もたれに体重を預ける。この屋敷の便宜上の主人はスヴェンだが、だからと言って小難しい報告を聞かされたくはない。
此方を気遣ってかやや大きめの声量で語られはじめた言葉を、茶請けにと出された焼き菓子を頬張りながら聞き流す。干した果実を使い作られたそれはエステルが好んで食していたもので、その殆どは彼女の小さな腹に収まっていたけれど、時折気まぐれのようにスヴェンにも分け与えられることがあった。甘みの強いこの菓子は好みとは言い難かったけれど、それでもこの二月にも満たない期間で食べ慣れてしまった味だった。
口の中に残る甘味と酸味を冷めきった茶で流し込んでいるうちに報告も終わったようで、執事が一礼して部屋を出て行く。何か次の仕事でも命じられたのか、その様子は常になく忙しない。
「で? 結局は誘拐で決定ってことかよ」
「……状況から言えばそうなるでしょうね。王家の血族は第六感に優れた方が多いですし、なんらかの異常を察知したエステルが屋敷外の様子を見に行き、そのまま……と言うのが、現状で最も可能性の高い仮説でしょうか」
勿論飽くまでも想像の域を出ない話ではありますが、と苦い顔をするフランの口元に大きめの焼き菓子を押し付け、それ以上の言葉を遮る。子供扱いも甚だしい行動に彼の表情が僅かばかり歪むが、流石に菓子を頬張ったまま文句を零すような不作法を冒すつもりはないようだった。
「という事は、誘拐犯探して嬢ちゃん取り返せばいいんだな」
こちらを非難するようなフランの視線を無視し、スヴェンは勝手に話を進める。非頭脳労働者のスヴェンにとっては、フランの出した結論さえあれば十分だった。情報の信頼度や推理の経緯など、わざわざ聞くだけ時間の無駄にしか思えない。そんな内心を察したのかはわからないが、フランもそれ以上自身の推察について語るのは諦めたようだった。
「……その結論で問題はないかと思います。ですが、言葉で言うほど簡単な話ではありませんよ。現場の痕跡からある程度のことは推理できますが、そもそもこういった捜査は軍の領分です。仮に犯人の目星がついたところで、正面から踏み込んで対峙する権限は僕達にはない。下手に手荒なことをすれば、牢に入れられるのは貴方のほうです」
「はぁ……それならどうしろって?」
「そうですね……一先ず、確証が得られるまでは秘密裏に調査を進めてください。苦手分野ではありますが、こちらとしても少し手を打ってみます。……幸いにして貴方は庶民出身の外国人で陛下のお気に入りです。言い訳の効かない状況でなければ、多少の問題行動はそちらに長けた方々が上手く揉み消してくれるでしょう。貴方がエルの手で招かれた救世主だと言う説だって、少なくとも陛下は信じている訳ですし」
「身も蓋もねぇ言われようだなそりゃ。……ま、ここで悶々と膝突き合わせててもしゃあないし、とりあえず調べて来いってんならやってやるよ」
指示は頼むぜ、と付け加え、スヴェンは柔らかなソファーから腰を上げた。小難しい話を聞くのはどうにも肩が凝るもので、軽く伸びをすれば関節がバキバキと悲鳴を上げる。お貴族様の流儀に合わせてやるのは大変だとボヤいてみれば、呆れ果てたような視線が容赦なく飛んできた。
「まずはエモンタール邸付近の調査をお願いします。変わったことがないか、屋敷の外から伺う程度で構いません。気になることは余すところなく報告してくださいね。なお場所については、あとで地図を用意しておきます」
「おう。……そう言や、さっきの認識なんとかの話は気にしなくて良いのかよ? あの話を信じるってんなら、何だって誤魔化し放題だろ。怪しいだの怪しくないだの見てわかるもんじゃなくなりそうじゃねーか」
「……詳細不明の超常現象を論理的な考察に組み込むのは、実質不可能です。気にするなと言うのも無理な話かもしれませんが、それによって判断を変える必要はないと、少なくとも僕は思います。……極論を言ってしまえば、今こうして貴方と対話している事さえ何者かに作られた妄想ではないと言う証拠はないのですから」
目を伏せそう零すフランの表情は暗い。その様子はやはり幼い顔立ちに不似合いで、何処となく落ち着かない気分にさせられる。
「や、まぁ、さすがにそいつは考えすぎだろ。下手に考えてもドツボにハマるだけってのは同感だけどな」
「……貴方は、何とも思わないんですか? 己の見聞きしているものが全て、紛い物かも知れないと言うのに。一度、考えてみてください。他人の言葉も己の記憶も、全てが信用に足るものではなくなるとして……貴方はまだそうやって、呑気に笑っていられると言うのですか?」
「あー……そりゃまぁ、気分は悪ぃな。つっても、そんな思いつめた顔するほどのもんでもねぇだろ」
わざとらしく肩を竦めて見せると、フランの視線が鋭さを帯びる。とは言え相手は自身より頭一つ小さな子供、睨まれたところで微笑ましさこそあれ威圧感など無いに等しい。
「なんつーか、そもそも信用できるもんじゃねぇと思うんだよな、言葉やら記憶やらってのも。人は嘘つくもんだし、覚えたこともそのうち忘れるもんだろ? お前みたいなお国の仕事してる奴らはそう言う訳にも行かないのかも知んねぇけど、そうギシンアンキ?になりすぎるのもよくないぜ?」
そう茶化してフランの頭を乱雑に撫でてやると、苛立った様子で手を振り払われる。
「……貴方に理解を求めようとした僕が愚かでした」
「そこまで言う程かよ……」
「ともかく、エル及びエステルの能力について現段階での考慮は不要です。貴方の独断行動を否定する気はありませんが、それについて僕は一切の責任を負いませんので心に留めておいてください」
冷ややかな口調でそう言い置き、フランは逃げるように部屋を後にする。常に無く感情的なその様子に軽く肩を竦めつつも、スヴェンは黙って彼の小さな背を見送った。
同刻、貴族街某所。
「……私はこんなものを連れて来いなどと指示をしたつもりはないが?」
窓の無い狭い部屋に、怒りを帯びた男の声が響く。
「ですが閣下。この娘は確かに王家に連なる存在です。何故あのような場に居たのかは不可解ですが、如何様にも利用できるかと」
「だから何だと言うんだ! こんな面倒事の種を拾って来おって!」
「この娘さえ居れば、貴方様の目的はもちろん、その上を目指すことも可能になります。どうかお怒りをお静めください。この娘は、きっと貴方のために役立つ存在となるでしょう」
流れるように言葉を紡ぐ男の腕に抱かれ、宵闇色の幼子がくつくつと嗤う。蝋燭の揺れる炎を映し込んだ鮮血色の瞳が、薄暗い部屋の中でも不思議と存在感を持って煌めく。
「……貴様らはこの私に反逆者になれと言うのか」
「いえ、そのようなことは……けれど、閣下ならばきっとこの娘の価値を理解し使いこなすことができるでしょう」
「…………そうか。ならば……」
声を落とし密談を続ける男たちの視線を受け、少女は怖気づく素振りもなく嫣然と微笑んで見せた。