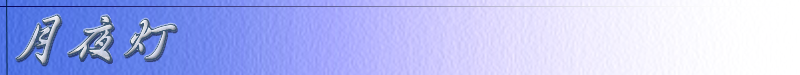
『海上の覇者』なる二つ名で呼ばれたスヴェンではあるが、実のところ一月前までただの船乗りであった。近海を周遊する貿易船に乗り、荷物の上げ下ろしや船内の雑役をこなす水夫で、荒事に縁がないわけではないがそれを本分としたことなどない、ごく一般的な平民として暮らしていた。それがどうして剣闘士というものになり、歯の浮くような二つ名など持つ羽目になったのか、実のところ当の本人としても全てを理解してはいない。勿論、他人の謀略に流されるまま貴族になるなどと言う、出来の悪い与太話の当事者になる心当たりだってありはしなかった。
それ以前に、この国に来た経緯についてでさえ、彼が認識していることは少なかった。ある夜、仕事中に前触れもなく嵐に巻き込まれたこと。その時、海に放り出されたこと。そして目が覚めたら、見知らぬ土地、しかも聞いたこともない国におり、貴族だという男の屋敷に保護されていたということのみである。
目覚めた当初、当然の如く混乱するスヴェンに、屋敷の主であるエセルは冗談とも本気ともつかない顔で言ったのだ。
「お前は、我らが神が引き寄せたこの国の救世主なんだよ」
王城に着いたスヴェンが通されたのは、聖女の間と呼ばれる部屋だった。壁一面に繊細な彫刻が施された上、美しい女性の像が鎮座するその空間は、王家の宗教行事に用いられる由緒正しい儀式場である。流石に気後れするスヴェンを余所に、先導するカーラはまるで自室のように足を進めていく。背後からエセルに小突かれ渋々部屋に入れば、見知った顔が二つほど上座に控えているのが見えた。
言葉一つ交わさずに、四人の貴族がそれぞれ立ち位置を定める。宗教儀式特有の静謐な雰囲気が満ちる中、部屋の中央に跪かされたスヴェンの正面で、カーラが優美な仕草で剣を掲げた。背後に同じように膝をついているエセルに小声で促され、スヴェンも応えるように腰に差していた剣を掲げる。
古臭く持って回った言い回しで、聖職者風の衣装を纏った貴族が言葉を紡ぐ。淡々と発されるそれは儀式における定型句のようなもので、内容は聞いていなくても問題はない、と事前にエセルから聞いていた。身も蓋もない話ではあるが、スヴェンにとっては有り難い。
「……以上をもって『海上の覇者』ことスヴェンの叙勲の儀を終了する。異論のある者はこの場で申し出よ」
いくつかのやり取りの後、カーラの凛とした声を合図に、傷の付いた長剣と小綺麗な宝剣を交差させ儀式は終わりを告げる。短くはない話にすっかり気を散らしていたスヴェンを余所に、その場に居るたった三人の立会人は胸に手を当てカーラへと向き直る。
「ラシュレイ家の長として、国の理を担う者を代表し賛同いたします」
「同じく、ヴェルデ家当主として、エルの御名の元、賛同の意を表明致します」
「シルヴェストル家当主列びに彼の者の後見人として、殿下とご参集の皆様に御礼を申し上げます」
一拍置いて銘々が頭を上げると同時に、カーラが大きく溜息をついた。その相貌には茶番でしかない儀式に対する苛立ちが滲んでいるが、剣を腰に戻す所作に乱れはない。
「フラン、シーギス」
「はい。民籍登録は済ませてあります。陛下の客分として離宮に部屋も用意させました。書類は控えの間にありますので、後ほど押印をお願いします」
名を呼ばれただけで淀みなく答えを用意して見せたその少年も、フランデリク・ラシュレイと言う名のれっきとした貴族だった。良くて成人したばかりかという見た目に違わずこの場では最年少だが、王の信頼は厚く、内政を裏表から支える国家の中枢の一人だ。聞くところに寄れば、ラシュレイ家は創国当初から王の補佐を勤める慣わしらしく、彼もそのために幼い頃から修練を重ねてきたらしい。
「……明晩、聖地に案内する予定になっている。離宮からなら俺が案内すれば事足りるはずだ」
紫の瞳に発言を促され、神官服の男が口を開く。代々聖地と神殿の管理を担うヴェルデ家当主、シーギスムンド・ヴェルデ。エセルやカーラとは子供の頃からの付き合いだという彼は、スヴェンにとっても馴染み深い相手だった。この国の歴史や神話について教えるなら適任だから、と言う建前の下、ここ一ヶ月体よくスヴェンの見張りを押し付けられた苦労人だからだ。闘技会の準備は神殿の管轄外。手が空いて居たのは確かなので断り切れなかったと言うお人好しである。
「聖地ってあれか、前に言ってた……とりあえず神と王と聖女がどうのこうのって言う」
「いい加減に創国の話くらい覚えてくれ……王宮の更に奥、デュランベールの守護神エルを祀る大神殿と代々の王の墓がある地をあわせて聖地と呼ぶ。創国王デュランが王となる前に神殿でエルの力を得、自らの死後はその地に埋葬するよう命じたのが始まりだ。また、聖女エステルも聖地で一生を終えたとされている」
「あーはいはい、そうだったっけな。んで、その聖地とやらに何の用なんだ?」
「……説明したはずだ。昨日も、先週も、最初にここに来た時も」
眉間に深く皺を刻み、シーギスは溜息をついた。その手には一冊の古ぼけた本が握られている。この国の聖典であると言うそれは、この一月で何度となく見せられた代物だ。創国の神話から始まり、これまでにエルが授けた奇跡の数々が記されていると言う有り難いものらしいが、スヴェンにとってはちり紙ほどの価値もない。
「守護神エルはデュランベール王国が危機に瀕すると、その度何らかの奇跡を起こし国を救ってきた。具体的な伝承は割愛するが……その力をもって歴史に名を残すような英雄を王に引き合わせたことも少なくない」
「ここまで来てお勉強かよ……」
「嫌なら一度で覚えろ……お前が真に英雄、もしくは救世主となり得る人材かどうかは、エルの御心のみが知ることだ。そこでまず、守護神を祀る大神殿に赴き、神託を受けることとなる。神託は誰もが受けられるものではないが、歴代の王、または英雄達の中にはエルとの対話を行ったものも少なくはない。幸い明日は満月だから、」
「……ま、とりあえず、エルと話せたら儲け物、ってくらいの気持ちで挑めばいいさ。状況に文句も疑問もあるだろうけど、俺らにはどうしようもないことだしな。会えたら直接エルに直談判すればいい」
話が長引きそうな気配に気づいたのか、シーギスの手から聖典を取り上げ、エセルが割って入る。いつの間にか残りの二人は立ち去って居たらしく、聖堂内には彼ら三人しか残っていない。仲がいいのか悪いのか、どちらにせよ協調性のない連中だと、スヴェンは内心溜息をついた。
「……エセル。まだ話の途中だ」
「無駄だって、碌に聞いてないだろこいつ。とりあえず明日はエルに面通し。これさえ解ってたら問題ないよ。……とりあえず、勉学より先にこれを渡しておかないとね」
そう肩を竦めると、彼は派手な礼服の懐から掌ほどの金属板を取り出した。中央に羽を広げた鳥の紋章、周囲に細かい模様と文字が刻まれたそれは手に乗せれば思いの外重く、鈍く光って存在を主張している。
「これがお前の身分証になる。国王陛下不在の叙勲とは言え、これでれっきとした貴族身分になった訳だからいろいろ融通はきくはずだよ。本当ならあわせて紋章印も渡すんだけど、悪いけど間に合わなくて」
「へいへい、何でもいいぜ。とりあえずこれがあれば外にも出れるんだろ? もう軟禁生活は懲り懲りだ、明日は街にでも繰り出すさ」
話を遮るように手を振り、金属板を胸元のポケットに仕舞う。晩餐会用に用意された衣装は装飾過多で全くスヴェンの好みではなかったが、着心地と機能性においては文句のつけようがない出来だった。普通に街で買ったら幾らするのか庶民のスヴェンには想像もつかないが、いつか金に困ったらこれを一番に質に入れようと心に決めている。
「……外出は構わないが、行くのは中央街区だけにしておけ。他の地区は警備体制が万全ではない。それから、日没後は城門の跳ね橋が上がるから王城への出入りはできなくなる。余裕を持って戻るように。あと……」
「お前は俺の母親か何かかよ。ガキじゃねぇんだから大丈夫だっての。ったく、これだから聖職者は嫌なんだ」
大きく溜息をつくと、スヴェンは二人に背を向ける。儀式は終えた。必要なものも手に入れた。そうなれば、もうこのようなところにいる理由はない。彼らは貴族にしてはマシな部類には入るけれど、それだけだ。無駄に心を許す必要も、仲良しごっこに興ずる必要もない。
そうして意気揚々と出ていったスヴェンが、与えられた自室を探して聖堂に舞い戻るまであと半刻ほど。彼の王都生活は、順風満帆とは言い難いようだった。