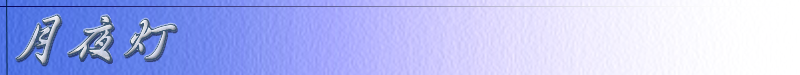
その晩は眩しいほどの満月だった。
王都の民達がすっかり寝静まった頃、スヴェンは離宮まで迎えに来たシーギスと共に聖地と呼ばれる地へと向かっていた。彼の宵闇に溶けるような濃紫のマントも、黒にも見える灰色の髪も、目印としては幾分心許なかったが、この天気では流石に見失うこともない。幸いにして道は相応に整備されており、さほど苦労することもなく目的地へと到着する事ができた。
王宮の更に奥、王都デュランで最も堅牢なその場所にひっそりと建つ神殿。華美な装飾も物々しい見張りもない、ただ大きいだけの石造りの建物。しかし何故だか奇妙な威圧感を放つ不思議な場所が、この国の聖地だ。
「この神殿は創国以前からここにあったと伝えられている。元々ここに住んでいた民が土着の神であったエルを祀るために用意した、という説が有力だ。創国王デュランがエルの加護を得たのもこの神殿で、それ以来王族や神官、英雄たちがエルに祈りを捧げ御声を聴く場所となっている」
つらつらと説明を続けながら、シーギスが扉を押し開ける。彼の持つ蝋燭の灯りだけで照らされた神殿内は外よりも余程暗く、まるで人の侵入を拒むかのように見える。とは言えまさかここで怖気づく訳にも行かず、スヴェンは苦い表情のまま神殿内部に足を踏み入れた。
こつり、こつりと足音を響かせ、二人は礼拝堂らしき広間の中を進む。使う者が居らぬまま無機質に整列したベンチも、足元を照らし揺らめく炎も、本音を言えば不気味でしかない。そんなスヴェンの思いを知ってか知らずか、シーギスは広間の最奥まで辿り着くと、徐に手元の蝋燭を吹き消した。
「ニーナ、居るか」
吸い込まれそうな暗闇の中、常と微塵も変わらぬシーギスの声が響く。それに応えるように現れたのは、スヴェンの胸の高さほどもない小さな人影が一つ。暗色のローブとベールで全身を覆ったその姿は、贔屓目に見ても化物の類か不審者にしか見えない。例えそれが二人の前で静かに頭を垂れていようとも。
「彼女はニーナ。この聖地を守る神官だ。エルからの神託を受ける巫でもある。ここでの儀式に関しては彼女に一任させてもらう」
「はぁ?」
思わず顔を顰めたスヴェンの視線から逃げるように、シーギスは目を伏せる。表情こそ大きくは変わらないものの、僅かに泳ぐ視線は隠し切れていない。
「おい、何企んでやがる」
「彼女の方が俺より余程実力は確かだ、安心してくれ。……後は頼んだ、ニーナ」
「はい、お任せくださいませ。ではスヴェン様。こちらへ……」
スヴェンの言葉を半ば無視してシーギスが踵を返すと、ニーナが面を上げる。顔立ちも身体付きもすっかり隠され判断がつかないが、彼女、と呼ばれた通りその細く掠れた声は確かに女のものだ。立ち去った後ろ姿と目の前の神官を交互に見遣り、スヴェンはため息をつく。騙し討ちのように置き去りにされたが、文句を言うのは明日でもいいだろう。
「女の神官なんてのも居るんだな。あんたも貴族?」
「私はエル様にすべてを捧げた身。性別も身分も持ってはおりません」
囁くような声での返答に、スヴェンは軽く肩を竦める。秘密主義な女は魅力的だが、生真面目な聖職者と言うのはそれ以上に苦手なタイプだ。早々に世間話は諦め、促されるまま足を進める。
「この先は中庭へと続いております。あちらの祭壇の前で守護神様に祈り、天啓をお待ちください」
ニーナが広間の隅に飾られた分厚い布を手繰ると、アーチ状に開いた裏口が顕になった。月光に照らされた中庭は広く、数本の木が植えられては居るが閑散としている。ぽつりと置かれた祭壇は大きいがやはり質素で、供物らしきものも置かれてはいなかった。
「アンタはどうすんだ?」
「私はここでエル様に祈りを捧げねばなりません。どうぞ、あちらへはお一人で……」
深々と頭を下げられてはそれ以上食い下がる気にもなれず、スヴェンは憂鬱になりながらも祭壇まで進んだ。茶色とも黒ともつかない色の石で出来たそれは、人一人が横になっても十分なほどの大きさがある。ニーナは神殿内に残るのだし、余りにも長くなるようだったらここで寝るのも手かもしれない。そんな罰当たりなことを考えながら、スヴェンは祭壇の前に膝をつく。
その瞬間。まるで吸い込まれるように意識が途切れた。
目を開くとそこは薔薇園だった。木漏れ日の中、形も色も様々な花弁が、広くはない庭に整然と並んでいる。中央にそびえ立つ石造りの塔から蔓薔薇のアーチで繋がれているのは、見覚えのある質素だが大きな神殿だ。
「…………なんだよこれ」
絞り出すように呟いて、再度辺りを見回した。夢だと思おうにも、噎せ返るような薔薇の香りが現実逃避の邪魔をする。これがエルの奇跡だと言うのなら、只人のスヴェンは諸手を上げて降参するしかできない。
「結局来てしまったんだね、スヴェン」
どれほどの間呆けていただろうか。不意に背後からかけられた声に、ゆっくりと視線を動かす。木漏れ日色の長い髪、柔和そうな笑顔。どこか既視感のある容貌の青年が、白いローブを纏い立っていた。
「アンタは……エル、か?」
「ふふ、そうだね。ぼくはエルで、エルはぼくだ」
細い指先がスヴェンの頬を撫でる。温度のない手は女のように滑らかで、どこか作り物のような印象を受けた。
「キミを呼んだのはぼくの意思じゃない。それでも、零れた水は戻らないものだ。キミが英雄となるか志半ばで倒れるかは判らないけれど、この地に住まうデュランの子の一人に変わりはない。エルはキミを歓迎し祝福するよ」
「……そう言うのいらねぇから、元いた場所に返してくれ、ってのは?」
「それは聖地のこと? それともかつてキミが暮らした海の上?」
エルは男とも女ともつかない声音で、まるで歌うように言葉を紡ぐ。その様子は飽く迄も楽しげで無邪気だ。
「前者ならば心配はいらない。ぼくはキミの肉体に触れることはできないからね。今この時は夢幻。キミの魂に触れ、少しだけぼくの中を見せているに過ぎない。後者なら……頷くことはできないかな。ぼくにはもうそんな力はない。今を維持するので精一杯だ。それに、戻るべき故郷がある者は、そもそもこんな細やかな波に攫われたりしないものだからね」
「好き勝手言いやがって……流石神様とやらは違うな。庶民の事情なんぞ知ったことない、ってか」
吐き捨てるようなスヴェンの言葉にも、エルは顔色一つ変えはしない。柔和そうな微笑を浮かべたまま、我が子でも見るかのような目でスヴェンをじっと見上げている。
「納得が行かないと言うなら、キミにひとつ真実を教えてあげよう。人の世では、諦めも覚悟も外からもたらされることのほうが多いものだしね」
徐に、冷たい掌が額に押し当てられる。ふわりと舞い上がるような風が吹き、エルの纏う衣がさらさらと揺れた。彼を照らす暖かい光に思わず目を閉じれば、それを合図に脳裏に知らない光景が流れ混んでてくる。
明るく栄えた街、楽しげな民の姿、凱旋する軍勢。まるで走馬灯のように流れてくる情報は、雪の中倒れる見知らぬ男の姿を境に暗いものへと変わっていく。激しくなる戦線、陰謀渦巻く宮中、食事に盛られる毒。映るのが知らない顔ばかりであることに意識せず安堵していると、やがてコマ送りの場面は終わり暗く濁った空が視界に広がった。
桶をひっくり返したような激しい雨が振り始める。轟々と吹く風に荒れ狂う海が遠くに見えた。視界と音の臨場感とは裏腹に、雨に濡れる感触はない。奇妙な感覚に目眩を覚えると、エルの手が宥めるように髪を撫でてくる。
「今見せているのは、この国の転機となった大災害の記憶……ある年の収穫祭の前夜、今日のような眩しい満月の下で、ぼくはこの国に大きな干渉を行った」
視界が霞むほどの雨の中、突然雷鳴が鳴り響いた。地面が暴れるかのように揺れ動き、海面が生き物のように押し寄せてくる。村を、畑を、都市を、自然の暴力が容赦なく襲い、奪っていく。
永遠に続くかと思われるような嵐が終わり、空と海に静寂が戻った後。そこには、始めから国などなかったかのように、ただ静かな海が広がっていた。
「ぼくは三百年蓄えた力を使って、デュランベールをこの海の底に沈めた。内にも外にも敵の居ない、理想郷を作るために」
エルの手が離れれば、流しこまれていた映像が止まる。目を開き周囲を見回しても、ただただ平和な花園があるだけだ。広すぎる海も、嵐も、そこには残滓さえ残ってはいない。
「……国一つ滅ぼしといて何が守護神だよ。悪魔の間違いじゃねーの?」
「元よりそれは紙一重のものだろう? ……それに滅ぼしてなどいないさ。オルランドの……この国の王のために必要なものを選別しただけ。民は地上と変わらぬ生活を送ってる。ぼくの造った深い水底の王国で皆、幸福に生きている」
幸せでたまらないとでも言うかのようにエルは笑う。その鮮血色の瞳には悪意も後悔もなく、ただあの海のように静かに凪いでいた。