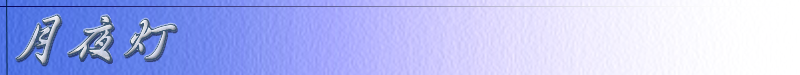
「ぼくの言葉が信じられないと言うなら、塔に登ってみるといい。きっとキミの星が見つかるよ」
そう言い置くと、エルは風にとけるように姿を消した。あり得ない退場の仕方に、やはり夢の中なのだなぁと今更な感想を抱きながら、スヴェンは言われるがまま塔に登る。『星見の塔』と名が刻まれた円形の塔は質素で、人の足跡で幾らか削れた狭い石段が延々と続くだけのつまらない塔だ。このまま何事もなく目覚めてしまいたいと言う後ろ向きな願いも虚しく、スヴェンはやがて石段の終わりまでたどり着いた。
塔の頂上は、予想に反し何も無いただの見張り台だった。腰ほどの高さしかない柵の向こうに、霞がかったような街の風景が見える。先程まで明るかった空は絵の具で塗りつぶしたような深い藍色に変わっていて、それが唯一の違和感だった。
「……星なんて一個も無いじゃねーか。適当なことばっか言いやがって」
舌打ちをしたところで、それを咎める声はない。居るのか居ないのかさえ定かではない相手に一方的に毒づくのも馬鹿らしく、スヴェンはガシガシと頭を掻く。やはり神なんて信じるものじゃないと独り言ちていると、不意に背後に人の気配を感じた。
「二度も同じ手は喰らわねぇぞ、この嘘つき…………って、誰だお前」
振り向くとそこには、十歳にも満たないであろう幼い少女の姿があった。石柵の上に腰掛けた彼女は、エルによく似た紅い瞳で、表情一つ動かさずにじっとスヴェンを見つめている。
「あー……なんだ、嬢ちゃん。お前もエルの仲間かなんかか?」
僅かに腰を屈め話しかけるも、少女は身動ぎひとつ返さない。漆黒の髪が風に揺れ、白く生気のない頬を擽るように揺れる。
「……だんまり決め込むってんならそれで良いけどよ。んなとこ居たら危ねえぞ?」
そうため息をつき足を踏み出した瞬間。風に煽られたのか、ふわりと浮かぶように少女の体が傾いだ。
まるで吸い込まれるように倒れて行く少女に、スヴェンは咄嗟に手を伸ばす。薄紅色の唇がゆるりと弧を描き、幼い顔が蠱惑的に歪んだ。伸ばされた手を掴むことなく、彼女はゆっくりと塔から落ちていく。静かに、その鮮血の瞳にスヴェンを捉えたまま。
少女の体が地面に叩き付けられるその直前、スヴェンの意識は再び白に彩られた。
目を開いた瞬間、酷い頭痛に襲われた。安い酒を一晩中飲み明かした後のような不快感に頭を抱えながら、薄く開いた目で周囲を見回す。傾いた月の光に照らされたその部屋は、どうやら寝室のようだった。部屋の中央に鎮座する寝台こそ大きく立派なものだったが、それ以外には何もない寂しい部屋である。
広いベッドの上には、こちらに背を向けて一人の青年が横たわっている。シーツから覗く髪は、塔の少女と同じ艶のある黒色だ。これもまだ夢の中なのだろうかと訝しみながら、スヴェンは青年へと手を伸ばす。
「動くな」
手を上げるや否や、足を踏み出すよりも早く、首元に冷たい何かが押し当てられた。
「怪しい真似をしたら首を落とす。貴様は何者だ?」
静かな声には、抑え込まれたかのような殺気が宿っている。思わず振り向こうとすれば、僅かに刃が喰いこんだ。皮一枚を正確に裂くその動きは、相手の言葉が脅しなどではないことを明確に物語っている。
重厚な鎧を纏った彼は、この部屋の主の護衛だろうか。大柄な筈のスヴェンよりも更に上背があり、そのアイスブルーの鋭い瞳には一分の隙もない。幸いにして今すぐ斬り捨てられるという訳では無いようだが、状況は良いとは言い難かった。
「……大丈夫だよ、ラディス。ただのエルの悪戯だ」
張り詰めた空気を破ったのは、ベッドの上の青年だった。気怠げに身を起こした彼が軽く手を上げると、ラディスと呼ばれた鎧の男が静かに剣を下ろす。半歩下がって跪いた彼の手は未だ油断なく柄にかけられているが、青年もそれには言及する気が無いらしい。
「初めまして、スヴェン。僕はオルランド。せっかく来てくれたのに、こんな姿ですまないね」
そう微笑んだ彼の頬は、月明かりの中でもはっきりと判るほど青白い。白い寝間着の襟元を直す指先は細く、握手の一つもすれば折れてしまいそうな有様だった。
「……いや、俺こそ悪ぃな、起こしちまって。具合悪いみたいだが大丈夫か?」
「気にしないでいいよ。きみのことはエルから聞いていたし……それに、今夜は調子が良いみたいだ。きっときみが来てくれたからだろうね」
小さく息を吐くと、オルランドはそっと寝台を降りた。人並みの域を出ない身長と明らかに線の細い体躯を持ちながら、真っ直ぐにスヴェンと向き合う彼に弱々しさはない。柘榴石のように暗く光る瞳が、じっとスヴェンを見上げている。探るような色を持つその視線は到底居心地の良いものではなかったが、何故だか反論の言葉は出てこない。
長いようで短い見つめあいの後、ふとオルランドが目を伏せる。その口元には笑みらしきものが浮かんではいたが、それ以上に困惑の色が濃いように思えた。
「……きみは不思議なひとだね、スヴェン。それに、少しばかりおかしな来訪の仕方でもあったようだ。……でも、僕はこの国の王として、きみのことを歓迎するよ。僕の手が及ぶ範囲でなら、出来得る限りきみの力になろう」
「そりゃありがとな……って、王? アンタが?」
「おや……エルには何も聞かされていなかったのかな。確かにあまり王らしいことはしていないけれど」
くすくすと笑いを零しながら、年若い国王は白いシーツに腰を下ろす。言われてみればオルランドと言う名に聞き覚えはあったが、気付いたところで後の祭りだ。気を悪くした様子でないのが幸いだが、それこと本当に首を切られてもおかしくない不敬に今更ながら背筋が寒くなる。
「……もうすぐ朝が来る。案内をつけてあげるから、エルに攫われる前に早くお帰り」
彼の小さな手の動きを合図に、静かに部屋の扉が開かれた。背後に控えていた鎧の青年が国王に一礼し、スヴェンに視線を向ける。その鋭い目に負け軽く会釈をすると、オルランドは苦笑混じりに手を振って見せた。
促されるまま幾つかの部屋を抜け、暗く静かな廊下に辿り着いてようやく、スヴェンは肩の力を抜いた。柄にもなく緊張していたようで、首と頭が強張って重く痛んでいる。肩をゆっくりと回せば、バキバキと派手な音が鳴った。
その様子を、ラディスが表情なく見つめている。オルランドの言っていた案内と言うのが彼なのだろうが、危うく殺されかけた相手だ。スヴェンとしてはあまり嬉しい相手ではない。
「別についてこなくてもいいぜ? 朝になったらシーギスの奴が迎えに来るっつってたしな」
「いや……神殿までは送ろう。彼もこちらに居るとは思っていない筈だ」
一つに括られた銀髪を僅かに揺らし、ラディスは窓のない廊下に足を進める。その手が剣にかかっていないことを横目で確かめ、仕方なくスヴェンもそれに続いた。どうやら彼はお喋りな質ではないらしく、廊下には二人分の足音と金属が擦れる音だけが響く。
「お前、人に斬りかかっといて一言も無しってのは無いんじゃねぇの?」
根負けして沈黙を破ったのは、やはりスヴェンのほうだった。気の利いた話題選びなど出来はしないしする気もないが、黙っているよりは幾らかマシ、と言うのが彼の性分だ。そのせいで損をしたことも少なくはないが、持って生まれたものというのは中々変えられない。
「しかもよ、脅しならまだしも普通に切ったろ。死んだらどうしてくれんだよ」
「……それが私の職務だ。傷の手当はヴェルデ卿に頼んでくれ。……それに事情はどうあれ、尊い方の寝所に忍び込んだことに変わりはない」
「トウトイ方のシンジョ、ねぇ。相手が美人でエロいお姫さんとかなら心躍る単語だろうけどな。……ところでアンタ、名前は? ラディスでいいのか?」
「……家名はレスタンクールだ」
対するラディスは淡々と、眉一つ動かさず言葉を返す。面白みのない回答に、スヴェンは大げさに肩を竦めて見せた。この国の貴族というものは、概ね家の名や役職名で呼び合うのが常らしい。親しい間柄のみ愛称で呼ぶことが許され、本名に至っては主君か家長しか呼ぶことは無いという。何度となく説明された事柄ではあるが、姓さえ持たない平民のスヴェンには未だに馴染めない風習だ。
「まぁいいけどよ、なんでも。アンタもアレだろ、あの貴族連中のお仲間だろ? 聞いたことあるぜ、そのレスなんとかって名前」
「そう思ってくれて構わない。……語弊がありそうではあるが」
そうして弾まない会話を続けているうちに、やがて見覚えのある廻廊へと辿り着いた。広い庭には花など碌に咲いては居ないし、塔だって勿論無い。数時間前初めてここを訪れた時のまま、静かにひっそりと祭壇だけが置かれている。
言葉少なに立ち去るラディスを見送り、スヴェンはぼんやりと夢の中で出会った二人のことに思いを馳せる。国を沈めたと言っていたエル。彼の言葉は、あの光景は事実だったのだろうか。それにオルランドは彼をまるで友人であるかのように扱っていたが、神と言うものがそんな形で実在するものなのか。そして、名さえ知らないあの少女。エルと違って話題にも上がらない存在ではあったが、塔から落ちて行った彼女はいったい何者だったのか。
答えの出ない問いを胸に、スヴェンはただ白み始めた空を見上げていた。