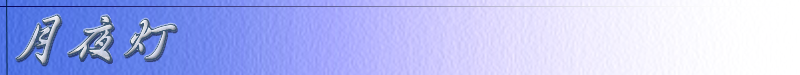
「何かご用でしょうか」
翌日。聖地を訪れたスヴェンを出迎えたのは、早朝だというのにかっちりと神官服を着込んだニーナだった。頭から胸までを黒いベールで覆い、更に同色の手袋をつけた手で箒を握る姿は、お伽噺の魔女を彷彿とさせる。夜ならまだしも初夏の明るい日差しの下には不釣り合いな格好だが、本人にそれを気にした様子はない。
そもそもこのデュランの街は、スヴェンが元居た港町よりも格段に涼しく過ごしやすい気候をしている。代わりに冬場は雪に覆われるそうだが、そんなことより肌を露出する女が少ない事実のほうがスヴェンにとっては問題だった。海の女達ほどとは言わないまでも、ナターシャ程度の露出があればニーナと話すのも格段に楽しくなるだろうに。
「……あの、ご用件は」
下世話な視線に気付いたのか、ニーナが感情の乗らない声で問いかける。その声に我に返ったスヴェンは、ローブの下に思いを馳せていた思考を何事も無かったかのような顔で引き戻し、漸く本題を切り出した。
「や、ちょっと神殿の壁剥がさせてもらいてぇんだけど」
「お引き取りください」
「いやせめて話くらい聞いてから断われって! 掃除でもなんでも手伝ってやるから!」
拒絶とともに閉じられようとする扉に、スヴェンは咄嗟に足を挟み込んだ。分厚い扉の隙間から差し込む光が、ニーナの顔をベール越しに照らす。朧気ながら見えたその表情は、案の定厳しいものだ。
「……私は神殿を預かる身です。無作法な行いを成される方をお通しする訳にはまいりません。どうかお引き取りください」
「大丈夫だって!ちょっとばかり確かめたいことがあるだけだ。それにほら、剥いだとこもちゃんとそれらしく直してから帰るしよ、安心しろって」
「お引き取りください。今すぐに」
小柄なニーナが全身を使って扉を押し返したところで、スヴェンが片手で押さえるそれはピクリとも動かない。その気になれば強行突破も容易ではあるが、女の家に押し入る暴漢のようで少しばかり気が引けるのも確かだ。
「あー……じゃあよ、とりあえず壁剥がねぇからどっか怪しいとこがないかだけ見せてくんね?」
「……怪しいところがあった場合、どうなさるおつもりなのでしょうか」
「そりゃ剥いで確かめて見るに決まって……いや違う違う、剥がねぇって、な? そうだな、どうすっか……ああそうだ、ちょっと穴開けて覗いてみるってのはどうだ? 腕が入るくらいあければ中も見えるだろうしよ。んで、何かあったら本格的に剥いでみようぜ」
名案だ、とばかりに胸を張ったスヴェンの腹に、ニーナが扉の隙間から箒の柄を叩きこむ。的確に鳩尾を突いたその攻撃により、幸いにして、300年の歴史を誇る神殿の内壁は守られることとなったのだった。
ことり、と小さな音を立て、水の入ったカップがスヴェンの横の地面に置かれた。鳩尾を押さえたまま恨めしげにニーナを見上げれば、彼女は気まずそうに顔を逸らす。彼女とて、まさか自分の攻撃ひとつで大の男がダウンするとは思ってはいなかったらしい。
「……ここは中で介抱するとか、そういう流れじゃねーのかよ?」
「…………敵対者に対する神官の武力行使は、戒律でも認められています。治療の義務はありません」
そう言いながらニーナは神殿の扉をしっかりと施錠し、蹲るスヴェンの横に腰を下ろした。治療はしないまでも、放置するほど薄情でもないらしい。神殿内に閉じ籠られるよりは余程マシだと言えたが、手が届かない距離を保っている辺り、気を許してはいないのだろう。
「なぁ、アンタ毎日ここに居んの?」
「ええ……時折ヴェルデ卿の御公務に御一緒させて頂いてはおりますが、それ以外はこちらで生活させていただいております」
「じゃあよ、奥のほうの壁に地下通路だか地下室だかがあるか知ってるか? 普段使いの部屋って感じじゃなさそうだったし、多分入口は隠してあると思うんだけどよ」
夢の中の記憶を辿りそう尋ねるも、ニーナは首を横に振るばかり。やはり自分の目で確かめるしか、と思いはすれど、ここで彼女から鍵を奪って神殿に入れば不法侵入そのものだ。この国の法に詳しくはないが、流石に牢にぶち込まれかねない行為は慎むべきだろう。
「……なら、ガキ見たことねぇか。黒髪で赤い目の……多分七つかそこらの女の子だ。多分、居るとしたらこの辺だと思うんだよな」
「こども……」
ぽつりと呟いたニーナとの距離を僅かに詰めながら、スヴェンは置かれていた水を一気に飲み干す。僅かに柑橘とハーブの香るそれは、だいぶぬるくはあったが爽やかで美味だ。
「何だったら、昔そんな子供が居たとかそういう情報でも良いぜ。守護神なんぞが普通に顔出す場所だ、亡霊の一体や二体じゃもう驚かねぇよ。もう燃えちまったらしいが、昔は後宮とやらにガキも居たんだろ?」
「……わかりません。私には何も……私はただ、ここでエル様とヴェルデ卿に与えられた日々を過ごすだけのもの……なにも、答えることはできません……」
「そうケチ臭いこと言うなって。何も誘拐しようだとか考えてる訳じゃねぇんだから」
取りつく島もないニーナの様子に、スヴェンは深く溜息をつく。元より数のない手がかりではあったが、これで軒並み潰れてしまった。他にあてと言えば、同じく聖地に居を構えているのであろうオルランドくらいのものだ。だが流石のスヴェンも、突然一国の王の居室を尋ねようとは思えはしない。不用意なことをすれば、次こそあの近衛に首を落とされかねない危険がある。
ならば次に行くべきは、気は進まないがフランのところだろうか。神殿の壁を剥ぐなど、ニーナと同じ聖職者のシーギスに言ったところで許可が出るはずがない。ならば何だかんだと物知りなフランのところにでも行って、隠し通路や何かの情報を得るのが順当なところだ。勿論それを素直に教えてくれるか否かは、甚だ疑問ではあるが。
「……貴方は、仮にその幼子を探し出したとして、どうなさるおつもりなのですか?」
「あ? ……そうだな、別にどうするとか考えて無かったけど……なんつーか、手が必要そうなら助けてやりてぇってだけだ。俺も助けて貰ったしな」
「助ける……」
ニーナが、本心を探るかようにじっとスヴェンを見つめてくる。ベール越しでも解る真っ直ぐな視線に、スヴェンは軽く肩を竦めて見せた。この国に来てから、この手の目線を向けられることは多かった。誰も彼もが、スヴェンが腹の底に何か隠してやしないかと疑ってかかってくるのだ。最初こそ不快感が勝ったが、今ではもう慣れてしまった気がする。
「貴方の事は一先ず信用して良いと、ヴェルデ卿は仰っておられました。スヴェン様は確かに、エル様が遣わし賜うたお方だと。……ならば私も、貴方を信頼するべきなのでしょう」
「はぁ……そういう義務的な信用貰ってもちっとも嬉しかねぇけどな。それくらい上司や神に頼らず決めろよ」
「私は一度は死んだ身……ヴェルデ卿に救われ、いまここに在るものです。あの方と、あの方の信じる神の忠実な僕である事が、私の唯一の意思です」
きっぱりと言い切ったニーナに、スヴェンは苦虫を噛み潰したような表情を浮かべた。彼女のような思考停止は、スヴェンにとって忌むべきものだ。彼が宗教や貴族と言うものを嫌う理由の一つでもある。だがそのような反応には目もくれず、ニーナは淡々と言葉を続ける。
「……神殿内のことでお話できることはありません。けれど、他のことでしたら……貴方にお話しても、問題はないのでしょう。けれど、どうか他言は無用に願います。私は俗世を捨てた身、過去は持たぬはずのものですから」
そう深々と頭を下げるニーナに、スヴェンはただ曖昧に頷くことしかできなかった。