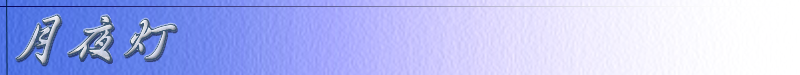
結論からいえば、ニーナの話は然して長くはならなかった。彼女は必要と思われることだけを掻い摘んで話すと、逃げるように神殿へと戻ってしまったからだ。
彼女から得られた情報は二つ。今は廃墟も同然となっている後宮に、有事の時のための隠し通路があるということ。そしてその後宮に、かつては幼い少女も数名暮らしていたと言う事だけだ。少女たちの容姿や生死は勿論、彼女が何故そのようなことを知っているかさえ、尋ねる前に立ち去られてしまった。追いかけて問い詰めようにも、しっかりと内側から閂が掛けられた神殿の扉は、最早スヴェンにはどうすることもできない。
「……まぁ、次のあてはできたことだし、ここらが引き際ってとこか」
そう独りごち、スヴェンは足早に聖地を後にする。この話は内密に、と再三釘を刺されてしまった以上、ここでばったり誰かに会いでもしたらまずいことになる。腹を探られ慣れはしたとはいえ、それでスヴェンの隠し事が上手くなった訳ではないのだ。少し追及されでもしたら、あっという間にボロが出るに違いない。彼女の『信頼』とやらに精々応えてやるためにも、それだけは避けねばならなかった。
「……やはり、こっちに来ていたのか」
然れども、世の中そう思った通りには行かないものである。聖地からそれほど離れもしないうちに、スヴェンは今最も会いたくない相手と鉢合わせてしまった。逃げ場もない一本道にて出会ったシーギスは、何故か昨日以上に疲れた表情をしている。
「あー……いや、別に何もしてないぞ?」
「第一声にそれが来る時点で信用ならん。……もう戻ると言うことは、用があったのは神殿だけか」
「おう。流石に一国の王のところにほいほい遊びに行くほど非常識じゃないぜ?」
得意げな顔で胸を張って見せれば、シーギスは深く溜息を零す。
「聖地に不法侵入しておいて威張るんじゃない。……それに、与えられた離宮を抜け出してうろついてる時点で十分非常識だ。頼むから大人しくしていてくれ」
「そう堅いこと言うなっての。つーかそこらに居た兵士だって別に止めなかったぜ? ったく、これだから聖職者は」
「聖職者として言ってる訳じゃ……まぁいい、衛兵が止めなかったのはおそらくカーラの差し金だろう。今後は、聖地や王宮内への侵入には制限がかかることになる筈だ。お前が人を探したいと言うなら協力はするが、できれば勝手な行動は……」
「へいへい、わかったわかった。神官様はいちいち小煩くて困るぜ」
ぱたぱたと手を振ると、スヴェンはシーギスを押し退けるようにして王宮への道を下りだす。おそらく正論を言っているのだろうが、わざわざ面白くもない彼の説教を長々と聞く気は無かった。聖職者達のトップに対し随分な扱いではあるが、幸いにしてそれを咎めるような相手はここには居ない。言われた本人でさえも、無理矢理切り上げられた話をそれ以上続けようとはしなかった。
元より聖地に用があった訳ではないらしいシーギスと共に、スヴェンは黙々と山道を辿る。しっかりと整備された小道の各所に立つ衛兵達が、通る度に姿勢を正し礼をしてきたのがやけに目に着いた。
「……ところでスヴェン。単刀直入に聞くが、ラシュレイ……フランとは、どこまで繋がってる?」
やがて王宮の敷地に辿くと、シーギスは僅かに声を抑えそう尋ねてきた。その真面目そのものといった表情からは、何の意図も読み取れそうにない。
「いや、繋がってるも何も、そもそも殆ど話したことねぇよ。確か最初にエルに会った後に、ちょっと話聞きに行ったくらいだな」
「そうか……お前の要請で動いているのかと思ったが、見込み違いだったか。すまない、おかしなことを聞いた」
「はぁ……何かあったのかよ?」
顎に手をやり思案顔をするシーギスを見下ろし、スヴェンは肩を竦める。貴族同士の腹芸に興味はないが、知らずに話を聞きに行っておかしなことに巻き込まれでもしたら敵わない。
「……昨日お前のことで話をしに行ったんだが、少し様子がおかしかった。フランはあまり自分から動くタイプではないから、おそらく誰かの差し金だと思ったんだが……」
「それで一番に俺を疑うってどうなんだよ……他に暗躍しそうな奴らいっぱい居るだろうが。金色のとか黒いのとか」
あからさまに苦い顔をするスヴェンに、シーギスはゆっくりと首を振って見せる。
「フランは国政の面においては非常に優秀だが、謀には向いていない。エセルは確実性に欠ける手段は嫌うから、余程でなければ使おうとはしない筈だ。カーラのほうは、昨日の様子を見る限りそもそも利害が一致しない。ラシュレイへの命令権があるのは陛下本人だけだし、無理強いをしてまで手の内に引き込む可能性は薄いだろうな」
「あーそうかよ。じゃあもうそこは陛下を疑っとけばいいじゃねぇか、順当に」
淀みなく語られる言葉を、スヴェンは頭をばりばりと掻きながら聞き流す。聖職者の性なのか、シーギスは何かにつけて話が長い。これでまだ話者か話題が女ならば多少聞く気にもなるのだが、残念ながら話に出てくるのは男ばかり、しかも面白くもない派閥の話ときては、聞いた情報も右から左に流れて行くというものである。
「そうか……陛下についても、何も聞かされてはいないんだな」
スヴェンの気が散り始めていることに気付いているのかいないのか、シーギスは独り言のようにそう零す。伏せられた宵闇色の目は、思考の海に沈むかのようににじっと宙を見つめている。
「聞いてるもなにも、何の話かさえ知らねぇっての……なんつーかさ、お前らもうちょっと自分らのほうで相談とかしろよ面倒臭ぇな」
「……確かにお前からすれば、理不尽なことばかりかと思う。だがこちらも、それぞれ背負うものも立場も違うんだ。同じ国を支える身分だからと言って当然一枚岩ではないし、必ずしも協力し合えると言う訳では」
「だーかーらー、そういうところが面倒臭ぇっつってんだよ!てめぇらの事情に俺を巻き込むな!」
苛立ちのままそう怒鳴りつけると、スヴェンは壁を力任せに蹴り付けた。身体の横を足が掠めて行ったにも関わらず、シーギスには怯えた様子はない。ただ驚いたような表情で、僅かに目を瞬かせたのみだ。そんな態度に、更に苛立ちが募る。
どいつもこいつも腹の探り合いに御執心。貴族たちは皆スヴェンの頭の上を通り越すように理解のできない遣り取りをし、好き勝手な事情を押し付けるばかり。庶民のスヴェンにだって、考える頭もあれば感情もある。エルといい貴族たちといい、人を駒のように扱うのも大概にしてほしい。
胸中でぐるぐると回るそんな言葉を舌打ち一つに込めると、スヴェンは派手に足音を立てながら、大股でその場を立ち去った。
怒りに任せ方角さえ確かめず歩き去ったスヴェンだが、ふと気がつけば見知らぬ場所へと辿りついていた。王宮の本殿から幾らか離れたその地には、聖地の神殿に似た古びた建物が一つ、ぽつりと寂しげに佇んでいる。辺りには衛兵の姿さえ無く、碌に手入れもされていない庭も相まってまるで廃墟の様な印象を受けた。
どこか薄気味悪い風景に踵を返そうとしたシーギスの背後から、ぶわりと強い風が吹く。ギィ、と軋んだ音を立て、入口の扉が揺れた。よくよく見れば一部に焦げ跡の残るそれは、壊れて閉まらなくなってしまっているようだ。元々は固定されていたのだろう、その足元には短い鎖と錠が落ちている。
「……ここが後宮、か?」
ふと頭を過った考えが、意図せず口から零れ落ちた。迷い辿りついた先が目的地だなんて余りにも出来過ぎているが、王宮の敷地内に廃墟がいくつもあるとは考えにくい。先程からひしひしと感じる気味の悪さも、この中で多くの女子供が焼け死んだのだと思えば納得もいく。
僅かな逡巡の後。覚悟を決めるように唾を飲み込むと、スヴェンは意を決してその建物へと足を踏み入れた。