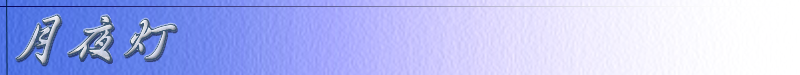
後宮。どことなく煌びやかな印象のあるその言葉とは裏腹に、スヴェンの侵入した建物はどこにでもありそうな寂れた廃墟であった。かつては室内を明るく照らしたであろう窓にはことごとく木板が打ちつけられ、室内を照らすのはその隙間から差し込む僅かな光のみ。その上、むき出しの石床には分厚く埃が積もり、歩く度に舞い上がる始末である。
ニーナからは、隠し通路の正確な場所も、どうやって隠されているかさえ聞けてはいない。広さだけは十二分にあるこの黴臭い廃墟で虱潰しに壁や床を探って回るなど、考えるだけで気が遠くなりそうな作業だった。
「……んだよ、誰か居んのか?」
やがてスヴェンが廊下の端に残る足跡に気がついたのは、入口から順に数部屋を探索し終えた頃だった。積もったほこりに一定の間隔で残されたその痕跡は、よく気をつけて見れば真っ直ぐに奥へと続いている。既に探索にすっかり飽きていたスヴェンは、一も二もなくその足跡を追いかけて奥へと向かった。駄目で元々、当たれば儲け物。元より然程期待してはいない。なので、足跡の先にあからさまに怪しげな階段を見つけたときには、思わず開いた口が塞がらなくなった。
「流石に出来すぎだろ、こいつは……」
階段の下の壁には、小さなランプが一つかけられていた。薄ぼんやりと明かりを放つそれは真新しく、油もたっぷりと残されている。さしものスヴェンも何かの罠ではないかと疑いを持つが、とは言えせっかく灯りがあると言うのにそれを捨てて進む気にもなれない。少しばかり警戒しながらもランプを手に取り、スヴェンは闇の中細長く続く地下通路を更に大股で進んで行く。
どれだけ歩いただろうか。早々に足跡を見失い、勘と夢の中の記憶を頼りに暫く迷った後、スヴェンはようやく新たな灯りを発見した。石の床に置かれたそれは手の中にあるランプと同じもののようで、通路の壁にぽかりと開いた部屋の入り口を小さく照らしている。
ようやく見えた追跡の終わりに、スヴェンの足取りも軽くなる。足元が整備されているのをいいことに半ば走るように薄暗い廊下を進み、勢いのまま部屋の中を覗き込んだ瞬間。何か光るものが、スヴェンの頬を掠めて行った。
「……ああ、やはり外れましたか」
カラン、と背後で何かが転がる音がした。じわりと一文字に熱さを伝える頬に手をやれば、僅かに濡れた感触が手に触れる。攻撃されたのだと認識するよりも幾らか早く、スヴェンは目の前の少年――フランに向かって身構えていた。
彼は先程頬を掠めたものと同じ小さなナイフを手に、静かな目でスヴェンを見上げていた。その横には、虚ろな目をした幼子が一人、ぼんやりと立ち尽くしている。ドレスこそ古びてボロボロになってはいたが、黒と赤を纏ったその容姿は確かに夢で見た少女そのものだった。
「それ以上近付かないで下さい。この少女が人質です」
部屋に足を踏みれようとしたスヴェンを、フランが静かな声で制する。握り締めたナイフは少女の首に押し当てられているが、当の少女に怯えた様子は見られない。表情一つ変えずただ静かに、鮮血色の瞳を虚空に彷徨わせているだけだ。
「……何のつもりだ? 場合によっちゃ、てめぇをぶっ殺してそこのガキを取り返したっていいんだぜ」
「僕がこの子を傷つける前に攻撃できる自信があると言うのであれば、試してみたらいいんじゃないでしょうか」
射殺すようなスヴェンの視線をものともせず、フランは淡々と言葉を続ける。
「貴方がこんなに早くここに辿りつくとは思っていませんでした。あと一日……いえ、一時間でもあれば、上手く行ったと思うのですが。運がいいのか……それとも、やはりこれも神の力なのでしょうか」
「あ? よくわかんねぇこと抜かしてんじゃねぇよ。なんでもいいから、とっととその嬢ちゃん解放しろ」
「拒否します。僕は……この子供を、ここで殺すのが最善だと、そう判断しているので」
フランは口元に笑みを作ると、一度大きく息を吐いた。握られたナイフが僅かに揺れる。刃渡りの小さなそれは、まだ幼い少女の命を奪うには十分ではあるだろうけれど、人を殺そうと言うには少しばかり頼りないものではあった。
「…………その判断とやら、いっぺん話してみろよ」
「何を言ったところで、貴方にとって、幼子を殺そうとする僕は悪人にしか見えないでしょう。話したところで時間の無駄かと」
「良いから言えっての! 何をどうやったらそんなチビ殺すのが一番って結論になるんだよ!」
「……貴方に、理解できるとは思えません。皆、この国の真実について知らなすぎる。何もかもを話したところで、きっと……」
フランが僅かに目を伏せる。手の内でナイフを弄ぶ様子はどこか不安げで、外見相応の幼ささえ感じさせた。
「理解できるかどうかなんて聞かなきゃ解んねぇだろうが。勝手に一人で納得してねぇでさっさと言葉にしやがれ。ガキならガキらしく大人に頼ってみろよ」
「……僕はこれでも成人してますよ」
「どっちにしろ最年少だろうが。良いから言えっつってんだよ。てめぇだって好き好んでガキ殺そうとか思ってる訳じゃねぇんだろ?」
一向に譲る様子の無いスヴェンに、フランは軽く首を振り少女を引き寄せる。その首元に再度ナイフを当て直すと、一度大きく息を吐いてスヴェンを真っ直ぐに見上げた。ランプの光に照らされ、土色の瞳が鈍く輝く。
「確かに、僕に覚悟が足りないのは事実です。この少女を手に掛けることにも、独りで重大な決断を下そうとしていることにも、迷いがあることは否定できない。……けれど、僕だって、伊達や酔狂でこんなことをしている訳ではありません。この子の存在は、確実にこの国の寿命を縮めます。誰にも知られず、闇の中で葬り去るべきものなんです。……貴方は何も見なかった。少女など始めから存在せず、ここでは誰とも会っていない。そう思ってはもらえませんか?」
「思える訳ねぇだろ。アホか」
「……そうでしょうね。なので、僕の計画としてはここで貴方に出会ってしまった時点で失敗なんです。本来ならば、誰にも知られずにこの子を殺し、証拠を隠滅して、何事もないような顔で日常に戻っていなければならなかった。エルの力を……いえ、恐らくはエルと同質の力を持つこの少女の力を、そして救い主たる貴方の素養を、見縊っていた僕の負けです」
「はっ……負けだってんなら、大人しく降参しやがれ。それとも殴り倒して止められたいのかよ?」
バキバキと指を鳴らしながらスヴェンが一歩距離を詰めれば、フランも少女を引きずるようにして同じだけ後退る。半ば八百長とは言え闘技大会優勝者のスヴェンと書類仕事ばかりのフランとでは、体格の差はもちろん腕力にも体力にも雲泥の差があった。人質を生かしきれないフランには、どう見ても勝ち目はない。二歩、三歩とじわじわと壁際に追い詰められ、フランの指先に力が籠る。
「貴方のその決断によって、この国が滅ぶかもしれない。それでも貴方は、自分の意見を……根拠にも欠ける、感情だけのその主張を、貫くことができますか?」
「難しい事は知ったこっちゃねぇよ。助けたいから助ける。それでいいだろ。後で問題が起きたら、そん時また考えりゃいいんだよ」
「……貴方と言う人は……」
僅かに逡巡した後、彼は少女の肩を掴む手はそのままにゆっくりとナイフを下ろした。
「少しだけ、話をしましょう。……僕は自分の決断を間違っているとは思いません。他の皆でも、同じ立場であれば同様の結論を出したはずです。けれど……それを一人で実行して、全ての責任を背負うだけの覚悟は、持てていない。……貴方のお嫌いな長くて複雑な話になりますが、聞く気はありますか?」
右手に小さなナイフをしっかりと握りしめたまま、フランはそう微笑んだ。