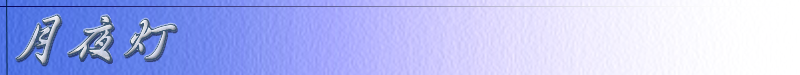
「僕の所属するラシュレイ家は、デュランベール貴族の中でも特殊な『真実を記し、後世に残す』と言う役割を担っています。その性質上、他の誰もが……陛下でさえ知らない情報にも、僕は触れることができます。ですから……この少女のことも、貴方から聞いた時点で既に心当たりがありました」
砂埃に汚れた石床に腰を下ろすと、フランはぽつりぽつりと語り出した。彼の隣には黒髪の幼子が腰を下ろし、相も変わらずぼんやりと虚空を見上げている。魂でも抜かれたようなその様子が気に掛からない訳ではなかったが、それも今は他所事だ。スヴェンは軽く首を振り、気分を切り替え口を開く。
「……つーことは、亡霊だとか言って脅したのは嘘ってことか」
「ええ。まさかあんな雑な嘘に騙されるとは思いませんでした。公に伝わる聖女エステルの容姿は、光を編んだような髪を持つ成人女性ですから」
悪びれもせずそう言うフランをじとりと睨みつけるが、彼は気にした様子もない。騙される方が悪いとでも言わんばかりの態度だが、こんなことでむきになるのも大人げない気がして、スヴェンは喉まで出かけた文句をどうにか飲み込んだ。代わりに手を軽く振って、話の続きを促してやる。
「この子の黒髪も赤い瞳も、国王陛下とよく似た特徴です。……僕の記憶にはありませんでしたが、大災害以前の後宮の内部記録を読み返せば、外見的特徴が合致する子供が存在した形跡がありました。命名式前の女児ですから、母親の名も本人の名も解らないのですが……おそらく、この少女は先王陛下の血を引く御子でしょう」
「……先王の子ってことはこの国の姫じゃねーか。なんでこんなとこに居るんだよ。それに、後宮の奴等は全員火事で死んだんだろ?」
「公的にはそうなっていますね。けれど、実際のところほとんどの遺体は損傷が酷かったため身元は特定できず、状況を鑑みた結果『全員死亡』という発表をした、と言う経緯があります。当時は時勢も混乱していて、悠長に遺体の数なんて数えていられるような状態ではなかったので、生き残りが居た可能性は零ではありません。……これは予想にすぎませんが、おそらく、事件発生後、火の手が回るよりも前にこの地下通路に逃がされたのでしょう」
ぱさり、と軽い音を立て、一枚の書面が投げ渡される。真新しい紙に丁寧に記されたそれは、この地下通路の見取り図のようだった。要所要所に書き込みがされ、後宮から現在位置までの道のりが丁寧に記載されている。軽く目を通しただけでもその図は複雑で、スヴェンが然程迷いもせずこの場所に辿りつけたのは奇跡のように思えた。
「王宮の地下通路は、万が一の時に王族の方々を逃がすために用意されています。けれど、外敵の侵入を防ぐためほとんどの扉は内側からは開けないようになっている。正しい出口を知るのは、僕のような記録者を除けば、王に連なるごく一部の尊い方しか居ません。……ここからは想像になりますが、彼女はその情報を教えられては居なかったのでしょうね。事件の日、通路の存在を知る者の手でこの通路に一人逃がされた彼女は、出口を見つけられないまま、ここに……聖地の地下にあるこの部屋に迷い込んだ。……ところでスヴェン。この年頃の子供が、飲まず食わずで生きられる期間を御存知ですか?」
唐突なフランの問いに、スヴェンはゆっくりと首を振る。問いの答えが解らずとも、彼の示唆したいことは流石に予想がついた。
「……誰かが食わせてやってたとか、そう言うのはねぇのかよ」
「勿論調べましたよ。けれど、そのような形跡はどこにもありませんでした。そもそも、地下通路の事を知っているのは王宮でも一握りの人間だけ。その見取り図だって特級の機密文書になります。……一切の痕跡を残さずこんなところで子供を養うなんて、できる者も、する必要がある者も居ないんです」
ちらりと少女に視線をやると、フランはスヴェンの手から紙を取り上げ、止める間もなくそれをランプの火に翳した。一瞬で燃え上がった見取り図は、石床に落とされてからものの数秒で真っ黒い燃えかすになる。その様子をぽかんと見下ろしていると、あんなものなくても帰り道くらい覚えていますから、とフランは僅かに笑って見せた。
「デュランベールの歴史を紐解けば、エルの奇跡には様々なものがあることが解ります。特に王族の方々は、幼い頃からエルの力の欠片を受け継いでいる事が多い。……この子が今こうして生きているのも、エルの神としての力を受けてのものだと考えれば納得がいきます。特に聖地は、エルの力が及びやすいとされる場所ですからね」
「はぁ……また現実味のねぇ話だな。そんで? 王族によくいるってんなら、死んだと思ってた姫さんが無事に見つかってめでたしめでたし、でいいじゃねぇか」
「……それで済ませるには、彼女は力を持ちすぎています。覚えているでしょうか。初めて聖地に行った際、エルが貴方に、貴方を呼んだのは自分ではないと語ったことを」
じっと真剣な目で見つめられ、スヴェンはどうにか記憶を辿る。余り記憶力に自信はないが、言われてみればそのようなことを聞いた気もする。その翌日に聖地での話を全て話して聞かせていたおかげで、辛うじて頭の隅に残ってると言った具合ではあったけれど。
「ずっと、引っかかっていたんです。人間一人を地上から海底まで生きたまま引きずり込むだなんて、普通ではできない芸当です。けれど、エルはそれを自分の意思ではないと言った。エルではない何者かの意思で、貴方がこの地に呼び寄せられたと言うのであれば……エルと同種の力を持つ別の何者かが存在すると言うことになるのではないかと」
「それがこの嬢ちゃんだ、ってお前は言うのかよ?」
「ええ。そしてその予想は、新月の晩の話を聞いて限りなく確信へと近付きました」
ゆっくりと視線を少女に移したフランに釣られるように、スヴェンも少女を見下ろした。一瞬、その鮮血色の瞳と視線が絡んだような気がしたが、その瞳に意志の光は宿っていない。精巧な人形のようなその容姿にどことなく気味の悪さを覚え、思わず目を逸らす。
「……考えてもみてください。デュランベールの守護神であり、陛下のために動くと言う至上命題を持つエルであっても、僕らは既に持て余しているんです。貴方もあれは化物だと言っていたそうですが、僕らの中でもそう言う意見を持つ者は少なくありません。……その『化物』に値するものがもう一つ存在するだなんて、今更言えるでしょうか。しかもこちらに関しては、目的も何もかもが不明で、いつ何をしでかすかもわからないんです。そんなものを身の内に抱えて、国の秩序が保てる訳がない……そうは、思いませんか?」
言い聞かせるように、フランが穏やかな声で言葉を紡ぐ。未だナイフを握り締めながらも、彼の表情は平坦なままだ。化物だと称した少女に向ける瞳にさえも、何の感情も浮かんではいない。
「なぁ。その秩序とやらは、ガキ一人の命より重いのかよ」
「当たり前でしょう。秩序も法も常識も、一度崩れれば沢山の人の命に関わるものです。それが死んだはずの子供一人の命で贖えるならば……例え相手が仕えるべき王の一族だとしても、迷うべきではないと僕は思います。……幸いにして、彼女にはもう恐怖を感じる心は残っていないようですしね」
フランが少女の目の前にナイフを翳しても、彼女は身じろぎ一つしない。恐らくこのまま刃を突き立てたとしても、碌な抵抗一つせずにゆっくりと死んでいくだろう。全身を赤く染め静かに目を閉じる少女の姿が、スヴェンには何故か鮮明に想像できた。
「……俺には、アンタが何を心配してるかなんてわからない。けど、アンタの想像した未来の中に、ハッピーエンドってもんは存在しなかったのか? この子も俺もお前らも、皆幸せで笑って暮らせる未来が絶対にないって言い切れるのかよ?」
「…………この世の中に、『絶対』なんてこと、そうそうありませんよ」
「なら俺は、この嬢ちゃんを殺すのには反対だ。誰かを犠牲にしなきゃ成り立たない平和なんて偽物だろ。……こいつがおかしなことしないかは、俺がちゃんと見張っててやる。エルと違ってちゃんと目の前に存在してんだ、例え化け物だろうがなんだろうが、俺が責任持って何とかしてやるさ」