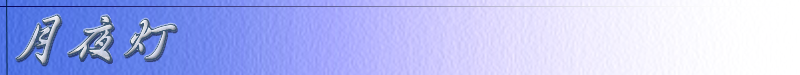
「……少し、現実的なお話をしましょうか」
幾許かの静寂の後、フランがゆっくりと息を吐いた。
「貴方の話は夢見がちで理想主義で、その上考えが甘くて現実が見えていない。到底地に足が付いた意見だとは言えません。他の方々の前で主張すれば、一笑にふされることでしょう。けれど……貴方がそう決断し、責任を負う覚悟があると、そう言うならば……貴方のような覚悟ができない僕には、何も言う権利はありません」
「……いや、十分ボロクソ言ってるじゃねぇかよ」
「そうでしょうか?」
内容の厳しさとは裏腹に、くすくすと笑う彼の瞳はこれまでに無く柔らかい。相変わらず表情の変化に乏しいことに変わりはないが、悪意からの言葉ではないのだろう。
「……スヴェン。この子の処遇については、貴方に一任します。僕はラシュレイの者として可能な限り貴方を補佐し、貴方の理想のために働きましょう。ですから……貴方の言う『未来』を、是非僕達に見せてください」
ナイフをそっと足元に置くと、フランは姿勢を正し優美な動作で頭を下げた。胸元に手を置いたその礼は、本来臣下が主君にするものだ。改まった雰囲気に気圧され、スヴェンは誤魔化すようにばりばりと頭を掻く。
「あー……まぁ、精々ご期待に添えるように努力してやるよ」
「お願いします。……先に、僕からの要望だけ伝えておきますね。この子の存在を、他人に知られるのは避けて頂きたい。それだけです。理由は先程話した通り……もちろん、相手が貴方と親しい他の貴族たちであっても例外ではありません。むしろ彼らに知られるのが一番困ります。……よろしいですね?」
「おう。アンタみたいに殺しに来られても困るしな」
頷くスヴェンを見上げると、あとで燃やしてください、と前置きし、フランは床に紙を広げる。迷いのない手つきで書き上げられていくのは、この王城の見取り図だ。流石に細かい部分は省略されているが、それが重要な機密であることは碌に学の無いスヴェンでさえ一目でわかる。
「まず確認ですが、このまま彼女を此処に閉じ込めておく、と言う選択肢はないという認識でよろしいですか?」
「当たり前だろ……んな監禁紛いなことできるかよ」
「では、どこか別の場所に匿う形になりますね。……現状、王城内に安全地帯は殆どありません。衛兵も文官も神官も、概ね他のどこかの家の息が掛かっている者がいますから。つまり、彼女の存在を他の方々に内緒にするという前提で話を進めるならば、何らかの手段を用いてこの王城内から街まで連れ出す必要がある、と言う事になります。できれば、誰の印象にも残らない形で」
まるで独り言のように言葉を続けながら、フランは次々と地図に印を書きこんでいく。人が多い場所少ない場所、衛兵の配置、時間帯に寄る使用人の動きなど、彼の口から零れる情報は膨大だ。謀には向かないが優秀、と言う彼の評価は的確だったようで、スヴェンがぼんやりと眺めているうちに彼の手元では脱出計画が着々と纏まって行く。
「いいのかよ、こんなもん部外者の俺に見せちまって」
「法には違反していますが、貴方が誰かに吹聴しなければ問題にはなりませんよ。……貴方を補佐すると言った以上、僕はもう共犯者です。出し惜しみをして成功率を下げるなんて愚かな真似はしません。幸い、王城から人目を盗んで脱出する程度のこと歴史上幾らでも事例がありますから、計画の立案は任せて頂いても大丈夫です」
「……なんつーか、お前の腹括るポイントがさっぱりわかんねぇわ……まぁ、そう言う頭使うのをやんなくて良いってんなら助かるけどよ。俺は嬢ちゃん抱えて走る練習でもしてればいいか?」
軽く肩を竦めると、スヴェンは汚れた床に座ったまま動かない少女に近付く。彼女の瞳はぼんやりと虚空を見つめており、スヴェンを映すことさえない。試しにと脇に手を入れ抱き上げてみても、そのまま天井に頭が付きそうなほど高く掲げてみても、彼女は眉ひとつ動かしはしなかった。
「……あまり乱暴な扱いはしないで頂けますか。血筋だけで言えば、その子は一応この国の姫なんですから」
「そうは言ってもよー……聖地じゃ普通に喋って歩いてたってのに今はこの調子だろ? なんか調子狂うんだよな。人形かなんかと話してるみてぇで」
片手でも軽々持てるほど細い身体を揺さぶり、スヴェンは眉間に皺を寄せる。飢えた子供など珍しくもないが、見知った相手が目の前で、となるとやはり話は違った。折れそうな身体を荷物でも抱えるように抱き直すと、事が済んだら一番に食事を摂らせることを内心誓う。幾らエルの力で命を保っていようと、腹が減らない訳ではないだろう。
「……では、名前でもつけてみたらどうでしょう。俗信の類は専門外ですが、真名には魂が宿るなどと言う話もあります。その子に正式な名前はありませんし、愛称の類も不明です。気休め程度ですが、無いよりはマシかもしれませんよ」
「んないきなり言われても思いつく訳ねぇだろうがよ……でもまぁ、いつまでもガキだの嬢ちゃんだの呼ぶ訳にもいかねぇし、ちゃんと考えてやんなきゃなぁ」
「ごゆっくりどうぞ。こちらはもう少しで終わりますから」
喋りながらも片時も手を止めないフランを尻目に、スヴェンは少女をじっと眺める。少し傷んだ黒い髪は土埃で汚れていたが、これもエルの力なのか気になるほどではない。姫だと言われて見てみれば、その幼い容姿にもどことなく気品があるように思えなくもないのが不思議なところだ。
ランプの炎に照らされた生気の無い白い頬は、塔の上で出会った日を思い出させる。エルによく似た紅い瞳。塔の石柵からゆっくりと落ちて行く姿。そして、人形めいたその容姿に浮かぶ、年齢に似合わぬ怪しげな笑み。
「…………エステル」
「……? なんですか、突然」
「こいつの名前。エステルってのはどうだ。聖女サマの名を貰うガキも結構いるって話だし、問題ねぇだろ? よし、今日からお前はエステルだ。気に入ったか?」
鮮血色の瞳を覗きこみながらそう告げると、ふらふらと宙を漂っていた視線とかちりと目が合った。人形のような無表情に見つめられ、幾分居心地の悪い気分になりながらもじっと見つめ返す。そして再度エステル、と呼んでやれば、幾ばくかの静寂かの後、その口元がほんの僅かに弧を描く。
「おっ、見たかフラン。こいつ今笑ったぜ!」
「気のせいでしょう。こちらの準備は整いましたので気が済んだら来てください」
「ったく、つれねぇ野郎だなぁ」
口では文句を言いながらも、ぐしゃぐしゃと少女の頭を撫でるスヴェンの表情は柔らかい。
結局、スヴェンの気が済むことは無く、痺れを切らしたフランに淡々と文句を言われることになるのは、その少し後のことである。
その後。結論からいえば、フランの立案した作戦は何の滞りもなく遂行された。
出入りの商人の荷馬車を使うと言う手垢のついた手法であったが、他の家の息が掛かっていない商人と話をつけられたのも、衛兵に一切見咎められずに動けたのも、偏に彼の持つ情報量が成せる技だろう。余りにもあっけない脱出劇は、スヴェンでさえも逆に不安になるほどだった。一人王宮を旅立った少女は、一先ずラシュレイ家の者に引き渡され、少しの間屋敷で匿われることになると言う。フランの話では、数日後にはスヴェン自身も離宮から出て街で暮らせるよう取り計らうそうだ。至れり尽くせり、とはこのことである。
優秀すぎる補佐役の暗躍を、数日の間普段通りに過ごすようきつく言い渡されていたスヴェンは何も知らない。彼はただ、窮屈な王宮から解放されること、そしてずっと心に引っかかっていた少女をようやく助けられたことを、何一つ疑うことなく喜んでいた。