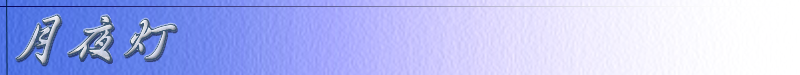
スヴェンとルカを乗せた馬車が向かったのは、中央通りに面した大きな店だった。鋏と針と糸が描かれた仕立て屋を示す看板の下には、既に立派な馬車が止められている。
「……エモンタール家の車ですか。また嫌な時に……」
「知り合いか?」
「ええ、まぁ……中央部貴族の一人で、先程お渡ししたリストの三枚目に記載されています。家格も発言権も然程高くはないので脅威ではありませんが……現当主が表立った反シルヴェストル派閥なので、可能ならば会いたくない相手ではありますね」
さっさと落馬して死ねば良いのに、と物騒な文句を零しながら馬車を降り、ルカは真っ直ぐに店へと向かっていく。会いたくないと言う割に、その足取りに迷いはない。
「殴り込みにでも行く気かよ」
「まさか。この時間、この店はこちらとの約束があります。たとえ相手が誰であっても、先約を優先せねば商人の信用は地に落ちると言うもの。殴り込むまでもなく、我々には店に入る権利があるんですよ」
にこりと微笑むその表情にどことなく不穏なものを感じ取り、スヴェンは肩を竦めた。揉め事を避けて通るタイプの主人に対し、従者のほうは少しばかり好戦的な気質らしい。
カランカランとベルを鳴らしながら、店の扉が開かれる。店員らしき者たちが、ルカとスヴェンを見て一斉に頭を下げた。それに倣わなかったのはただ一人、あからさまに身分の高そうな服を纏い濃灰色の髪を高い位置で括った壮年の男だけだ。
「失礼。約束していたシルヴェストルの者だが……取り込み中だろうか」
「は……申し訳ありません。只今ご案内を……」
「先客に対して挨拶もなしか。南の蛮族どもは礼儀を知らないと見える」
店員の言葉を遮り、男は敵意丸出しの瞳でスヴェンを睨みつけた。声を発したルカを無視してのその行動に、スヴェンは思わず顔をしかめる。
「初対面の他人をいきなり蛮族呼ばわりするのが礼儀かよ」
思わず口をついた文句に、相手の眼光が鋭くなった。拙いと思ったところで、一度発した言葉を戻すことはできない。怒りに顔を赤くした男は背も低く貧弱な体つきをしてはいるが、流石に貴族を拳で説得しては問題になるだろう。そう逡巡するスヴェンに大股で歩み寄る男の前に、わざとらしい作り笑顔を浮かべてルカが割って入る。
「申し訳ありませんエモンタール卿。このお方は我がシルヴェストル家の客人にしてラシュレイ家とも縁を結び、国王陛下直々のお声掛けで貴族になられた方でございます。ご多忙な中での来店となりますので、この辺りで失礼させていただきます」
「チェイン風情が。凋落した身で偉そうな口を利くようになったものだな」
「シルヴェストルの補佐役として必要なことをしたまでです」
淡々とそう言い放つと、ルカは鶯色の鋭い瞳をエモンタールと呼ばれた男に向ける。スヴェンよりは幾らか小さいものの十分に長身の彼に見下ろされ、男は僅かにたじろいだ様子を見せた。その隙を縫うように、ルカはスヴェンを促し店の奥へと足を向ける。
「……奴隷上がりの下賤の輩め。いつかエルの怒りに触れるぞ」
負け惜しみのように呟かれたその言葉が、広く豪奢な店内にやけに鮮明に響いていた。
「……つまり、結局問題起こしたってことか」
帰りの馬車の中、合流したエセルはそうあからさまに溜息をついて見せた。
「や、俺のせいじゃねぇよ」
「私は私の仕事をしたまでです」
「別にいいけどな……こうなるような気はしてたし。相手が喧嘩売る気でいるなら、角が立たないようにっていうのも無理な話だから」
お疲れ様、と心の籠っていない労いの言葉を発し、彼は思案顔で腕を組む。
「それにしてもエモンタール家か……仕立て屋に何の用があるんだ? まさかうちに喧嘩売るために待ち伏せしてたって訳もないだろうし」
「あの男ならやりかねないと思いますけどね。エモンタールの現当主は、自尊心ばかりが肥大した愚物ですよ。ああいう輩はまともな神経では思いもつかないようなことをやらかすものです」
冷やかに言ってのけるルカに、エセルは苦笑を零した。親子ほど年の離れた相手に大して酷い口ぶりではあるが、相手があの態度では仕方がないようにも思えてしまう。嫌悪を隠そうと言う気さえないエモンタールの顔を思い出し、スヴェンも思わず眉間に皺が寄る。
「それにしても、お前なんであんなに嫌われてんだよ。蛮族だの下賤の輩だの散々な言われようじゃねぇか」
「うーん……まぁ、正確なところはわからないけど、そういう扱いについては人種差別の一環だと思うよ。もう100年以上昔のことだけど、南の民は奴隷身分だった時代があるから」
多分一度は聞いてると思うけど、と前置きし、エセルは手元の紙にさらさらと図を描き始める。相当簡略化されたそれは、この国の地図のようだった。東から西へ向かい大きな川が二本流れるそれは、言われてみればどこかで見た覚えのあるものではある。
「デュランベール王国の東部と南部は創国当初は別の国の領地だった、って話は流石に覚えてるよな? そのうち、比較的気候や文化が近い東部は領主を挿げ替える形でも上手く統治ができたけど、砂漠地方で風習も人種も異なる南部地方の民は同じような支配は難しかった。戦勝国と支配地域って関係性もあるし、純粋なデュランベール人とは髪や目の色の差も大きかったのもあって、南方民を奴隷として扱う流れに反発は少なかったらしい。と言っても、王都以北では距離や気候の関係もあってあまり南方民奴隷は浸透しなかったから、主に中部と東部だけでの話だけど」
「……つまり何だ?」
「まぁ、簡単にいえば、かつてのデュランベール中東部では南方民は劣等民族扱いで、奴隷として使役するのが当たり前のことだったってことだよ」
時代遅れも甚だしい考えだけどね、と軽く肩を竦め、エセルは言葉を繋げる。
「転機は今から100年ほど前、賢王と名高い第17代国王陛下が奴隷制度を廃止なさったのがきっかけだ。彼の王自身が南方民の娘を正室に迎えたから今の王族には南の血が混ざってるし、公式の場で差別意識を顕わにする輩はそう居ないけどな」
「見方を変えれば、自分の惚れた娘を娶るために法を変えた愚王ですけどね。大恋愛の末の婚姻だったそうで、未だに劇場で人気の演目ではありますが」
「はぁ……そんな大昔のこと言われてもピンと来ねぇよ」
「他人事だと思うなよ。南方民の一番の特徴は金色の髪だ。お前がどこの誰であろうと関係なく、古い一部の貴族連中にとっては金髪ってだけで蔑視の対象だよ。幸い、そんな時代錯誤なことを言うの奴は街の方ではそう居ないけどな」
毛先のみ緩く波打つ金髪に指を絡め、エセルがにやりと笑って見せた。そこらの女よりも余程丁寧に手入れされたそれは編み込みと装飾品で彩られ、蔑視の対象などと自称する癖に随分と目を引く仕上がりになっている。
「純血のデュランベール人は髪や目の色素が濃い人種だからな。金髪にはだいたい南の血が混ざってるし、明るい目の色も多くは東や南の混血だ。……と言っても俺の場合、曾祖父まで遡らないと純血の南方民には辿り着かないくらいだし、南を故郷だとは思ったこともないんだけど」
「あー……それで俺のこともいきなり蛮族呼ばわりしてきたってわけか」
「そうそう、納得行ったか? ……まぁ、血や見た目のせいだけじゃないと思うけどな、ああいう輩が突っかかってくるのは。その辺りのことが言い掛かりの材料に使われやすいってだけで」
うちもだいぶ儲けさせてもらってるしね、と本音とも嘘ともつかない口調で零すエセルに、ルカがこれ見よがしに溜息をついた。