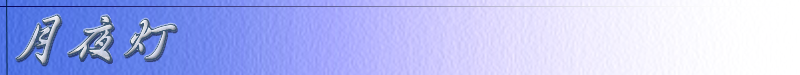
収穫祭に向け、貴族達が王都へ上る秋。人も物も増えるこの季節、通りには露店が立ち並び市街はにわかに活気付いてくる。
市街のシンボルである中央神殿においても、それは例外ではなかった。神殿の影響力が弱まりつつある昨今、民からの寄進だけでは十分とは言えない。表立って商売をするわけにはいかないが、薬やちょっとした飲食物の販売、加えて神殿敷地内での営業許可証の発行などでそれとなく金策を行うのがここ数年の常であった。
その日も、神殿の長にしてヴェルデ家の当主であるシーギスムンド・ヴェルデは一般の神官たちに混ざり朝から露店の設営にあたっていた。曲がりなりにも彼は王国貴族の一角を担う身、本来であればそのような雑用に勤しむ身分ではないのだが、人手が不足しているのだから仕方がない。祭り特有の賑やかな空気感も相まって、シーギスは相応に楽しみながら作業に励んでいた。
そんな彼が、敷地外で起きた小さな騒ぎに気がついたのは偶然だった。通りがかりの市民が噂していた内容を耳に挟んだのだ。彼ら曰く、えらく顔の整った若い軍人が広場で捕物をしている、とのこと。その言葉に嫌な予感を覚えたシーギスは、急ぎ話題の場所へと向かうのだった。
「何してるんだ、お前らは」
現場を探すのはさほど難しくはなかった。娯楽に飢えた市民たちが、それとなく通りかかった風を装いつつ人だかりを作っていたからだ。
「……シーギス? お前こそ何してるの、こんなところで」
声を掛けられたことで周囲の状況に気づいたのだろう、えらく顔の整った若い軍人――軍部の総司令官であるカラヴィアン・バシュラールは、舌打ちを一つ零すと辺りの市民を睨みつけた。鋭い眼光に野次馬達はばらばらと散っていくが、観客が減ったところで彼の足の下で男がもがいている光景の異様さに変わりはない。
「お前が騒ぎを起こしていると言うから……」
「は? 周りが勝手に騒いだだけだよ。私は自分の職務を果たしてるだけ。こいつが私の顔見るなり逃げ出したりなんてしなきゃ、そもそも追いかけたりもしなかったし」
逃げるってことは疾しいことがあるってことでしょ、と足の力を強めるカーラに、捕えられた男――スヴェンが呻き声を漏らす。ごりごりと背骨を抉る様に靴底を押し付けられる様は、見ているだけで痛そうだ。
「ったく、なんて軍人様だよ……別にヤマシイことなんてねぇっての」
「じゃあなんで私のこと見て顔色変えた訳? 隠し事はお前のためにならないよ。さっさと洗い浚い吐けば罪も軽くて済む」
「だからなんもやってねぇっての!」
再び言い争いを始めた二人に、シーギスは深くため息をついた。このままでは人目を集める一方だ。あまり関わりたいとは思えないが、醜聞が広がる前に仲裁に入るべきだろう。
「……双方言い分はあるだろうが、流石に場所を変えてくれ。神殿の前で騒ぎを起こされると風紀が乱れる。それにカーラ、お前はただでさえ目立つんだから……」
「へぇ、軍の仕事に神殿が介入するつもり? 相互不可侵の誓約を無視するつもりならこっちはこっちで考えがあるけど」
「そういうつもりじゃ……」
「あー、俺もう帰るな! また今度!」
矛先が変わったことに気がついたスヴェンが、カーラの足元から転がるように這い出すと脱兎のごとく走り去る。巨躯を苦にする様子もなくあっという間に姿を消した背中を、シーギスとカーラはぽかんとした表情で見送ったのだった。
「ったく、どんな勘してやがるんだあいつは」
無事逃走を果たしたスヴェンは、神殿から幾らか離れた路地でようやく足を止めた。辺りを見回せば、小さな本屋の前で佇む黒髪の少女の姿が見える。
「よし、ちゃんと待ってたみたいだな」
街中でばったりカーラと出会うと言う不運はあったものの、収穫はあったと言える。彼は自身を見て逃げようとしたスヴェンのことこそ目敏く発見して追ってきたものの、手を引いていたエステルには一切注意を払いはしなかった。先ほどの会話でも、スヴェンが少女を連れていることにも、王家以外には産まれぬという黒髪の子供が街にいることにも、一切触れてきてはいない。
異様と思える事態ではあるが、スヴェンはこの事象を前向きに受け止めていた。原理も何も解ったものではないが、少なくとも現在の状況下であれば、エステルが貴族連中に認識されなくて悪いことは一つもない。むしろ好都合でさえあるのだから、あれこれ論ずる必要性も感じなかった。
「おい嬢ちゃん。本は家に山ほどあるだろ。そっちで我慢してくれよ」
飽きる様子もなく本を見つめ続けるエステルに声をかければ、彼女は子供らしからぬ無表情で振り返る。相変わらず言葉はなく、笑うことさえ稀ではあるが、その態度にもすっかり慣れたものだ。別段子供好きという訳ではないスヴェンにしてみれば、泣いたり騒いだりする普通の子供より余程扱いやすく思えた。
「またカーラの野郎に会っても面倒だし、適当に買い食いでもしながら帰ろうぜ。そう高いもんは無理だけどな」
エステルの手を掴むと、スヴェンは緩やかな足取りで露店の立ち並ぶ大通りへと向かう。念のため市街の中心部は避けて道を選ぶが、それでもなかなかの賑わいだ。食べ物や飲み物を始め、衣類に装飾品、玩具の類など露店の種類も豊富で飽きることもない。
「別の街区でもあれこれ店が出てるらしいな。ま、ガキ連れでうろつけるのはこの辺りだけだろうが」
歩きながら一方的な会話を続けていると、ふとエステルの足が止まる。視線を追ってみれば、妙に古風で煌びやかな服装をした男女を囲ってまばらな人だかりができているのが見えた。
「ああ、劇やってんのか。ほんとなんでも揃ってやがるな」
演者たちの隣には『創国王デュラン』と演目が掲げられている。ここ数カ月だけでも飽きるほど聞かされた話ではあるが、どうやら民達の中では未だに人気を保っているらしい。
「気になるならちょっと見てくか? 立ち見ならそう高くもねぇだろ」
小さく頷いたエステルを抱き上げ、スヴェンは人の輪に近づいて行く。朗々とセリフを吟ずる役者になど欠片ほどの興味も持てないが、子供に合わせてやれないなほど狭量でもないのだ。請求書のことさえ無視すれば、懐具合も暖かいのも幸いして。
「おや……お子さん連れとは珍しい」
暫しぼんやりと演者を見つめていたところに突然声を掛けられ、スヴェンは跳ねるように振り返った。気配を悟らせることもなく背後に立っていたのは、奇妙な風貌の見知らぬ者だ。男にしては線が細いが女にしては大柄で、若いようにも見えるが年嵩なようにも見える、不思議な雰囲気を持った彼は、スヴェンを見上げにっこりと微笑んで見せる。
「ああ、失礼いたしました。私はここの者達の纏め役をしておりまして……仲間からはミミと呼ばれております」
あからさまに怪訝そうな顔をしているスヴェンを気にした様子もなく、彼は優雅に一礼して見せた。色の抜けたような白金の髪がさらりと流れ、金にも緑にも見える奇妙な色合いの瞳を隠す。見慣れない風体に、スヴェンは警戒を強め相手を睨みつけた。
「……俺らに何か用かよ?」
「いえ……少し、ご挨拶をさせていただきたかっただけですよ。あまりお引き留めしても申し訳ないですし、失礼しますね」
街中には似つかわしくない、引き摺るほど長い衣装の裾を揺らし、ミミはゆるりと歩き出す。
「またお会い致しましょう、スヴェン殿」
擦れ違い様、そう囁くように告げると、彼はふらりと人ごみに紛れていった。