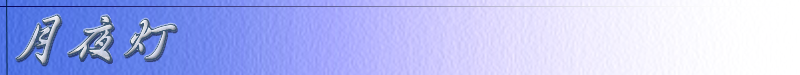
収穫祭前の朔の日。デュランベールの王宮では、王による午餐会が催される慣わしがあった。この午餐会は、現国王であるオルランドの治世となって儀式儀礼の類が随分と簡略化された中、現在でも行われている数少ない宮廷行事である。大別するならば私的な食事会であるとされるそれは、他の儀式に比べれば幾らか政治的な意味合いは少ない、らしい。
そしてその午餐会当日のこと。スヴェンはいつの間にか手配されていた貸馬車に乗り、王宮を訪れていた。見るからに面倒そうな食事会などすっぽかしてしまいたいところではあるが、流石に国王直々の招聘を粗末に扱う訳にもいかない。いくら顔見知りとは言え、権力者に逆らって良いことなど起きる道理はないのだ。
ため息をつきつつ、スヴェンは案内された部屋の壁際に腰を落ち着ける。幾つかの椅子の他、飲み物と果物が載せられたテーブルが中央に置かれた部屋は、どうやら待合室のようなものらしい。ぐるりと部屋を見回すが、十数名の客たちの中は知らぬ顔が殆どだ。
「あまり他の客人をじろじろ見るな。絡まれても困るだろう」
「……お前、俺の顔見るたび毎回小言言ってねぇ?」
人目を避けるように近づいて来たのは、いつもと然程変わらぬ装いのシーギスだった。聞くところによれば細部の装飾は異なるらしいが、神官服は元々正装の分類だからどちらにしろ問題はないそうだ。着慣れぬ礼服に苦労しているスヴェンとしては、羨めばいいのか憐れめばいいのか微妙なところである。
「今日は一人か?」
「ああ。陛下の私的な食事会という名目ではあるが、人目があることに変わりはないからな……あまり一つの家と親しげな様子を見せる訳にもいかない。参加者と言う意味なら既にエセルは来ているが、あいつはあいつで仕事中だ」
示された方向に視線を向ければ、恰幅の良い男と談笑するエセルの姿が目に入る。対話の相手はマリネルダという名の貴族だそうで、バシュラールやレスタンクールと並ぶ大領主とのことだった。シルヴェストルとは領地が接していることもあり良好な関係を築いているが、何故だかカーラには嫌われており、陛下からの覚えは可もなく不可もなくと言ったところ、だそうだ。
「へいへい……まぁその辺の事情はどうでもいいけどな」
小難しい派閥の話に流れかけていた会話を適当な相槌で切り上げ、スヴェンは手近な壁へと寄りかかる。
「で、他の連中は来ねぇの?」
「フランは今回も不参加だが、カーラとラディスは後から来るはずだ。おそらく着席後になるだろうから、用があるなら別に機会を設けたほうが無難だが」
「別に用はねぇよ……しかし、なんつーか、場違い感がヤバいな。若い連中ばっかりって訳でもなさそうだし」
「……そうだな。陛下と個人的に親しくしている面々の他にも主要な都市を治める貴族は概ね招待されているし、いつもより堅い席にはなるはずだ」
何事もなければいいんだが、と呟いたシーギスを他所に、スヴェンは退屈そうに欠伸を零した。
午餐会の本会場は、豪奢な飾り付けのされた大広間だった。広すぎる部屋の中央に、こちらも大きすぎる長テーブルが置かれ、揃いのデザインの椅子が添えられている。楽団でも抱えているのか、部屋の中には歓談の邪魔にならない程度に音楽まで流れている始末だ。そんな中スヴェンに用意された席は案の定末席で、きょろきょろと周囲を見回していても咎める者もいなかった。
やがて音楽が切り替わると共に、広間の扉が開かれる。扉の向こうにあったのはいずれも見知った顔ばかりだった。向かって左手に見覚えのある黒の軍服に身を包んだカーラ、右手に色違いの白い軍服に身を包んだラディス、そして二人に守られるようにして立つ、現国王であるオルランド。どこか緊張の滲む面持ちの三人が、ゆっくりとした足取りで広間のテーブルへと歩いてくる。
銘々が割り当てられた席の前に立つと、年老いた執事が午餐会の開催を告げ、葡萄酒の入った杯が配られた。本来ならばはすぐに飲んでしまいたいところではあったが、流石に食事会の作法については叩きこまれたのでそんな不作法はしない。最終的に、全て隣や正面の貴族の真似だけしてろ、と言う身も蓋もない注意に帰結していたが。
「――――我が国を背負う汝らと共に、この収穫祭を迎えられたことを喜ばしく思う。エルの祝福が汝らにあらんことを」
オルランドの無難だが短くはない挨拶が終わり杯を掲げれば、ようやく席に着くことが許される。公的な晩餐会ともなれば本題の食事に入るまでこの三倍以上の時間がかかると言うのだから付き合っていられない。これだから貴族は、と心の中だけで愚痴を零しながら、スヴェンは手もとの酒を煽ったのだった。
前菜らしい食べごたえのない数皿の後、ようやくスープの皿が供されたとき、事件は起きた。
「……カーラ。その皿は駄目だ」
挨拶以来ただ静かに食事を進めるだけだったオルランドが突然発した言葉に、周囲の貴族たちの表情が変わった。既にスープに匙を突っ込んでいたスヴェンも、隣の見知らぬ貴族に倣い神妙な顔を作って見せる。
「その皿は、食べてはいけない」
しんと静まり返った広間に、オルランドの声が凛と響く。暗赤色の瞳が、じっとカーラを見つめていた。その表情は真剣そのもので、冗談や悪ふざけの類には見えない。
「国王陛下、畏れながらお伺いします。それは、彼の皿に毒が盛られている、という意味でよろしいでしょうか」
沈黙を破ったのは、先程マリネルダと呼ばれていた貴族だった。見た目通り柔和そうな声色での問いに、オルランドは僅かに頷きを返す。王家の饗する宴で毒が盛られるなど、ものによっては王国史に残る大事件だ。途端にざわつきはじめた場内に、慌てた様子で隣室から近衛の兵が流れ込んでくる。
「……静粛に。軍総司令官として、この場を対応します。そこの近衛、神官を呼んで毒の確認を急いで。それから調理と運搬に関わった者を全て別室に招集。集まり次第事情聴取するから人を揃えて」
騒然とする場を収めたのは、意外なことに当事者の一人でもあるカーラだった。伊達に立派な軍服を着てはいないなとスヴェンが明後日の感想を抱いている間にも、兵たちは指示に従い規律正しく動きだす。
「では軍の方々の邪魔にならぬよう、我々は一度控えの間に戻るとしましょうか。皆さま方も、よろしいですね?」
ゆるりと立ち上がったマリネルダが、場にそぐわぬほんわかとした笑顔でぐるりと全員の顔を見回した。流石に国家で五本の指に入る大貴族の言うことに異論を唱える者も居ないようで、出席者たちも彼に倣い一人二人と席を立つ。結局、オルランドに付き添うように別室へと消えたラディスと、兵たちの指揮を取るためその場に残ったカーラを除き、全員が控室へと戻ることとなった。
「……なんかよくわかんねーことになってきたなぁ」
そうぽつりと呟いた言葉は、再びざわつき始めた室内で誰に届くこともなくかき消されたのだった。