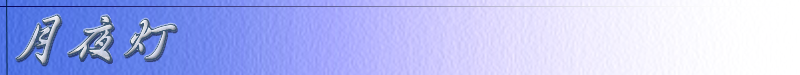
王宮を後にしたスヴェンは、渋々ながらその足でシルヴェストル邸へと向かっていた。勿論屋敷の場所など覚えてはいないが、優秀な御者は目的地の名を告げるだけで迷いもせずに馬車を走らせてくれる。その分の追加料金のことは一旦思考の外に追いやり、スヴェンはぼんやりと通りを揺られていった。
シルヴェストルの屋敷は貴族街の西門近く、大通りから少し外れた位置にある。当主自身の見目や所有する資産の量に反して屋敷の外観は極々一般的なもので、建物や敷地の大きさも隣の家と然程違いはない。とは言っても、貴族街の中に住まう以上、一定以上の規模と質は兼ね備えている前提だけれど。
玄関に馬車を横付けし呼び鈴を鳴らせば、すぐに使用人が出迎えに来る。挨拶も碌にせずいきなり用件を告げたスヴェンに、嫌な顔一つせず対応できるのは流石は名家の教育と言ったところだろうか。立派すぎて落ち着かない応接間に通され、何やら洒落た香りのする茶を飲みながら待つこと少し。姿を現したのは、予想通りシルヴェストル家補佐役であるルカだった。
「おう、ルカ。邪魔してるぜ」
「チェインとお呼びください。……王宮でのことは既に聞いています。届け物があると言う話でしたが?」
「大したもんじゃねぇけどな。エセルの奴がこの紙切れを届けろってよ」
差し出されたメモを受け取ると、ルカはスヴェンの正面に腰を下ろす。いつの間に書いたのかびっしり紙片を埋める文字列は、残念ながらスヴェンにはさっぱり理解できない内容だった。
「お前、それ見て何か解るのかよ」
「……覗き見を自供するような発言は慎んだほうがよろしいかと」
呆れたようにため息をつくと、ルカは紙片をそっと懐に仕舞う。入れ替わりに彼が取りだしたのは、鈍く光る五枚の銀貨だ。
「手紙の運搬、ご苦労様でした。こちらが今回の依頼に対する報酬です」
「は? いいのかよ、こんなに貰って」
「ええ。今回の貴方の行動には、それだけの価値があります。……ですが、そうですね。お手隙でしたら、もう一件仕事をお願いできないでしょうか。もちろんこちらにも報酬は出します」
机の上に、更に五枚の銀貨が重ねて置かれる。銀貨十枚といえば、未だ庶民感覚の抜けないスヴェンからして見ればかなりの大金だ。喉から手が出るほど、とは言わないまでも、貰えるものなら貰っておきたい。金は無いよりもある方が断然良いに決まっているのだから。
「別にいいけどよ。何するんだ?」
「封書を一つ、南西地区のある店まで届けるだけです。店の前までは当家で馬車を用意しますし、受付からは案内がつきますから、然程複雑な仕事ではありませんよ。勿論、届けた後は自由にして下さって構いません。……南西地区についてはご存知ですか?」
「おう。所謂、大人の遊び場ってヤツだろ」
ニヤリと笑うスヴェンに、ルカが軽く肩を竦める。王都市街の南西地区は、中央地区と同じく商店を中心とした街区である。中央市街よりも幾らか物価が安く雑然としているのが特徴で、賭場や娼館なども配置され夜に賑わう区域として知られていた。貴族街や中央市街に比べ幾分治安が良くないと言う欠点もあるが、女子供ならまだしも人より立派な体躯を持つスヴェンが気にするほどのものではない。
「じゃ、お言葉に甘えて、貰った10Dで遊んでくるとしますかね」
「ええ。ちゃんと先に用事を済ませてさえ貰えれば、後はどうなさろうと貴方の自由ですよ」
そうにっこりと微笑んで、ルカはスヴェンを送り出したのだった。
シルヴェストル家から馬車に揺られること暫く。すっかり日も落ち、街が闇に覆われる頃、スヴェンは指定された店へと到着した。大通りの角に面したその建物は貴族街の下手な屋敷よりも大きく豪奢で、見るからに高級そうな風情を醸し出している。
スヴェン単身でなら絶対に入れないであろう建物も、王宮帰りの礼装とルカから預かった紹介状があれば怖いものなど無い。受付でシルヴェストルの印が押されたカードを渡すだけで何も言わずとも個室へと案内され、暫し待つように告げられる。
「あら……シルヴェストル卿のお使いがいらしたと聞いたけれど、貴方だったのね」
やがて姿を見せた相手は、スヴェンにとっては懐かしい相手だった。エセルから彼女を紹介されたのはほんの数ヶ月前のことだが、もうずっと会って居なかったように感じる。美しく成熟した肢体に繊細な作りのドレスを纏い、妖艶に微笑む美女――ナターシャは、足音も立てずに室内に入るとスヴェンの正面の椅子に腰を下ろす。
「お久しぶりね、スヴェン……今はラシュレイ家でお仕事をしていると聞いたけれど、今日はどうなさったの?」
「ああ、いつもはそうなんだけどな。今日はちょっと……まぁ、日雇いみたいなもんだ。ルカの野郎から、この封筒届けるように頼まれてな。アンタに渡せばいいのか?」
「チェイン卿から? ええ、受け取るけれど……」
差し出された封書をテーブル越しに受け取ると、ナターシャは少しばかり困惑した表情を浮かべながら丁寧な手つきで封を切る。
「……貴方、この中身についてはご存じだったの?」
「いや? 流石に封開けてまで中身見たりしねぇよ。金もらって運んだだけで、内容に興味もねえしな」
「そう……それなら、きっとこれがあの方の意図なのね」
彼女の細い指につままれ取り出された紙は、どう見ても白紙そのものだった。封筒を覗きこんでみたところで、それ以外にはメモの一つさえ入ってはいない。
「んだよこれ。俺はただの紙切れ運ばされたってのか?」
「ええ、そうね……貴方、きっと餌にされたのよ」
ナターシャは困ったように頬に手を当てると、曖昧にそう微笑んで見せた。
月のない夜に、男は走る。闇に沈む宮殿は静かで、暗色の衣装を纏った彼の存在に気付く者は誰もいない。今宵の目的はただ一つ。平和ボケした貴族を一人、こっそり王宮から連れ出すだけだ。目的地の周辺のことは勿論、標的の情報も既に頭に入っている。簡単すぎる仕事だと、男は一人笑みを零した。
木を足掛かりに二階へと登り、窓からそっと室内の様子を窺う。灯りは既に消されており、寝台にはシーツを被り横たわる標的の姿があるのみだ。音をたてないように部屋へと滑り込み、口を封じるために用意した布を手にじわじわと歩み寄る。
標的までは僅か数歩。難なくその距離を詰めた男が、寝台へと手を伸ばした瞬間。ばさりとシーツが跳ね上がり、一瞬男の視界を覆う。事態を把握するより早く、何かが飛来する気配を感じ身構えた。僅かの後、予想より遥かに軽い感触で男の腕に何かがぶつかる。そこから飛び散るひやりとした感触と甘ったるい香りに毒を警戒しながら、彼は扉に向かい後退る標的を睨みつけた。
平均より小柄な体躯と宵闇でも目を引く金髪は、雇い主から聞いていた特徴と相違ない。いつ気が付いたのか、従軍経験のない若造にしては悪くない動きだ。こちらを真っ直ぐに見据える視線にも、怯えの色は見られなかった。それでもすぐに兵を呼ばなかったのは愚策だ。計画を変更し、相手に向かって構えを取る。
男の視界が、紅く染まる。